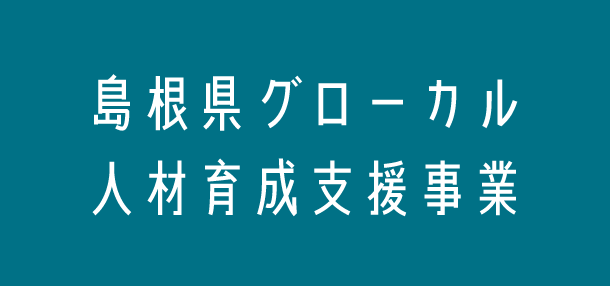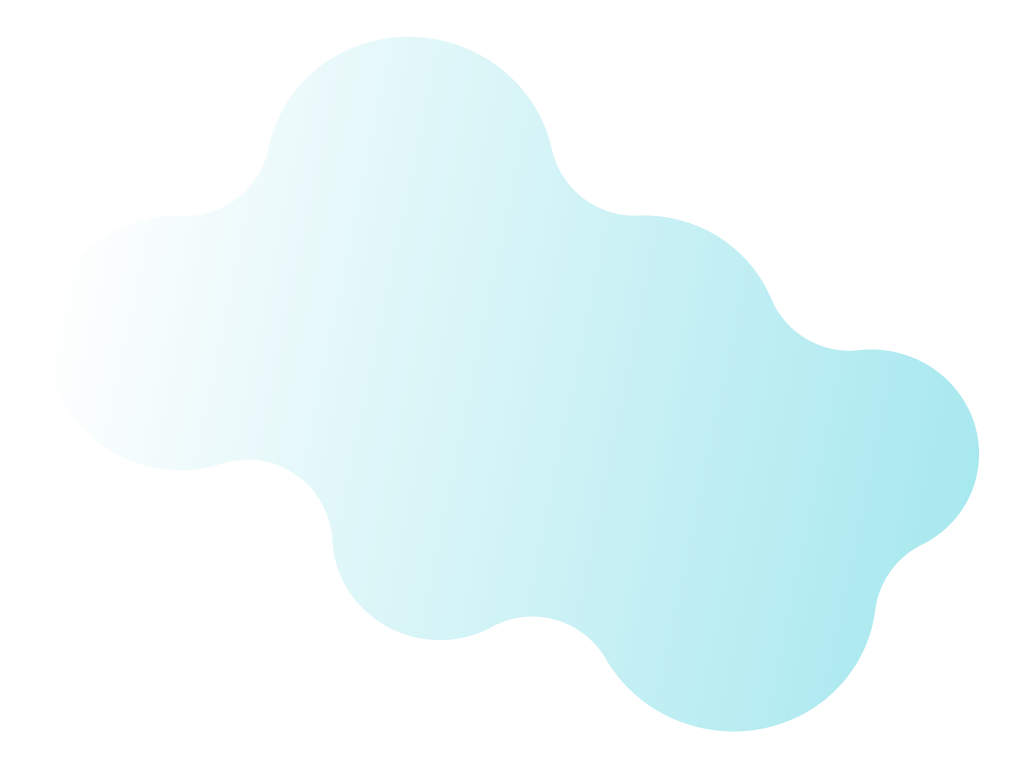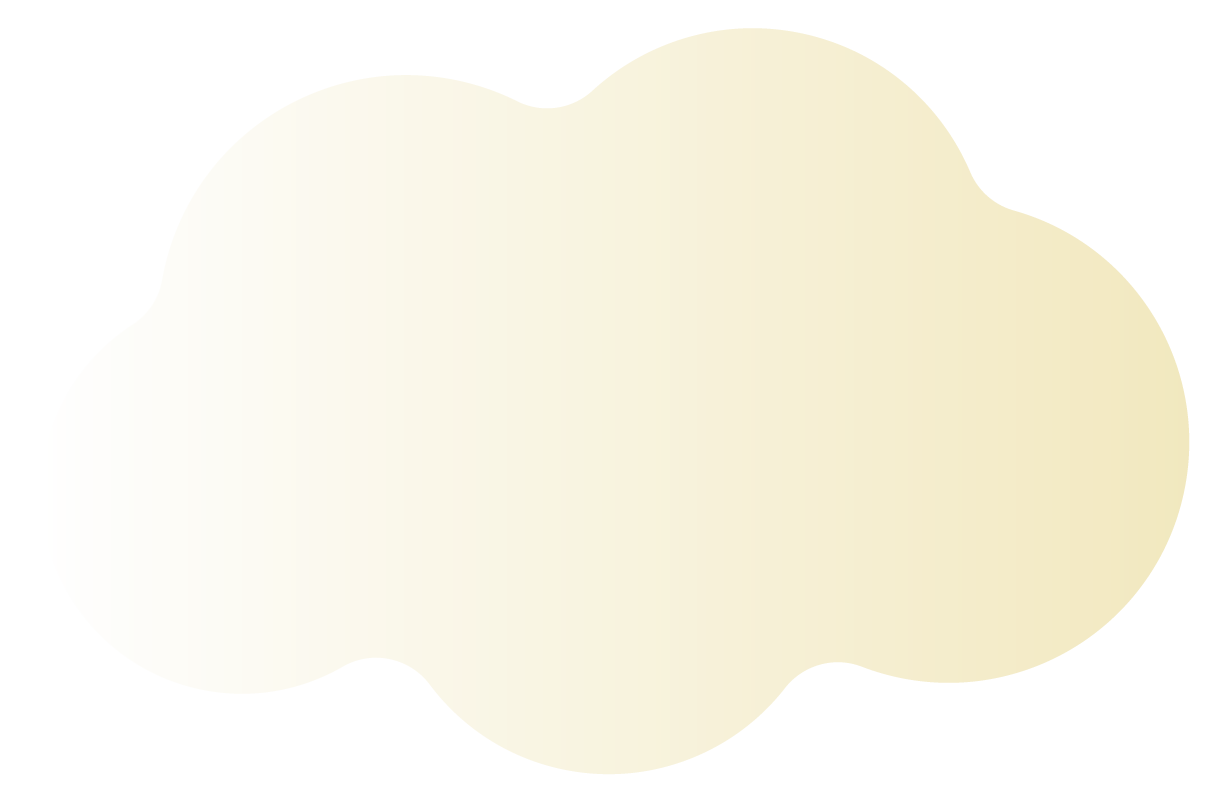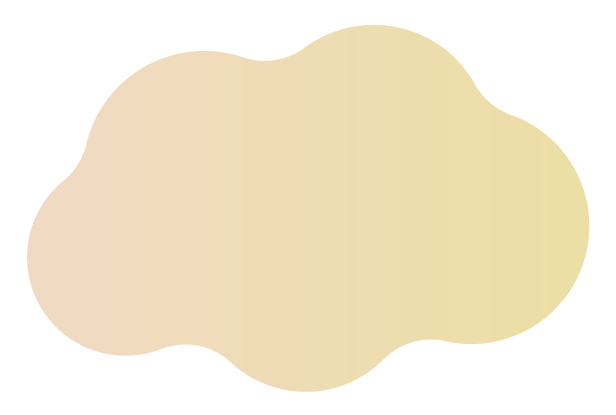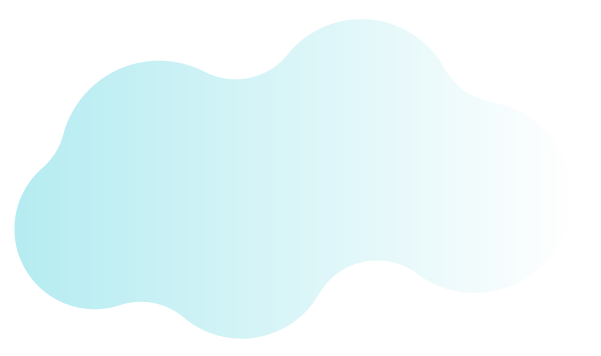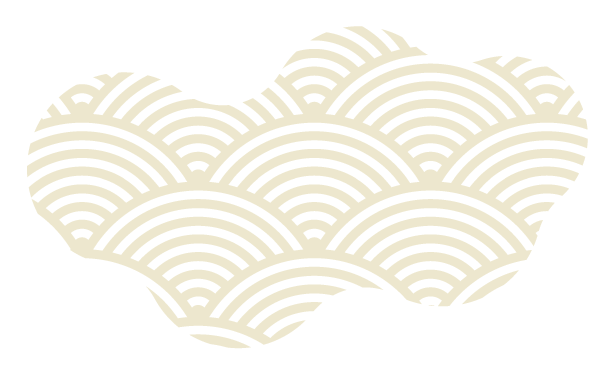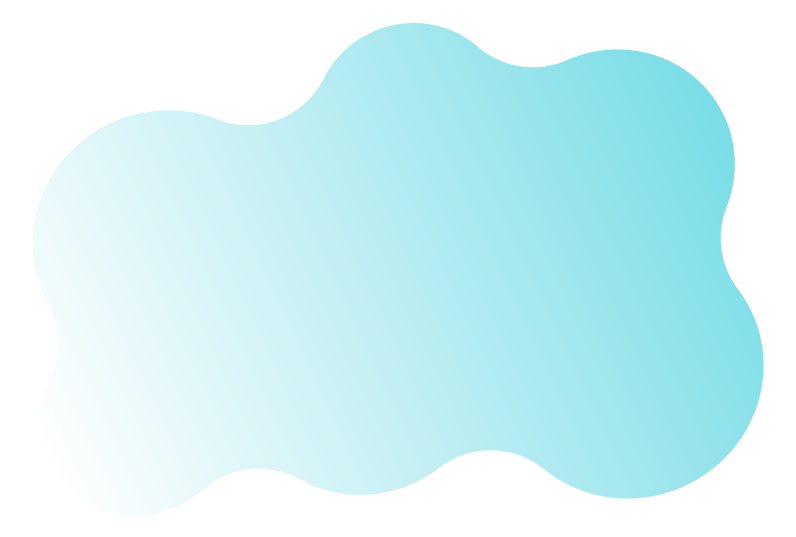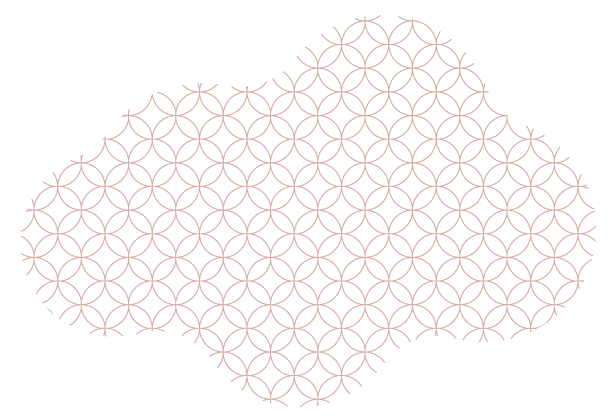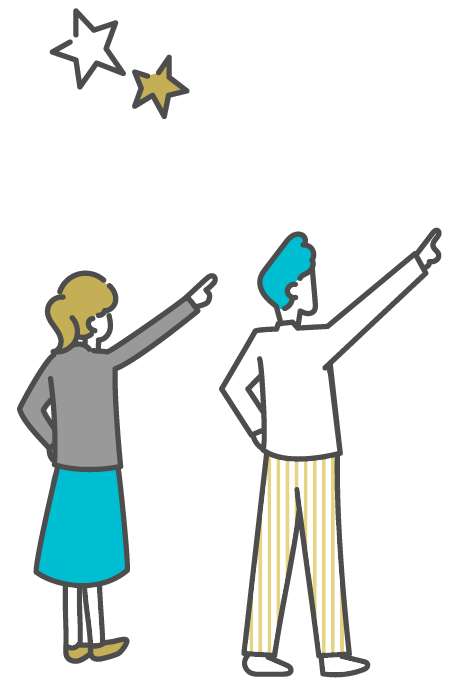第8回目 4月の活動 授業と中国各地の視察
今月の北京は、日によって寒かったり、暑かったりと気温の変動が大きかったです。特に4月の下旬頃は、気温が急激に上がり、昼間は半袖の服を着て歩いている人を多く見かけました。
中国語の学習
今月は、中間テストがありました。今回は、先生が事前に試験範囲や試験の実施日時などを一切教えないと言われました。このような形式で行われる試験は初めてだったので、非常に新鮮さを感じました。
テストの内容は、毎回の授業中に先生が解説してくださったHSK(漢語水平試験)の問題や課題として出される単語の穴埋め問題など、普段から授業でやってきた問題と同じような系統でした。何の準備や対策をする間もなく、突然実施されたので、現在の自分自身のありのままの実力を測られるような試験でした。
中間テストは、問題なく無事に終えることができました。中間テスト以降は、またいつも通り模擬試験を解いたり、過去問をといたりして、検定試験の対策を行っています。期末テストもまた、中間テストと同じような形式で実施されるかもしれないので、普段の授業から気を抜くことなく、より一層真剣に授業に臨みたいと思います。
学部の授業の受講
私は学部選択で、民族学社会学学部を選びました。授業は、社会学の専門科目である「性別社会学」と民族学の専門科目である「民族社会工作」という授業を履修しています。
特に、「性別社会学」の授業内容は興味深いです。最近は主に、男女の収入の格差問題や同性婚などに関する内容を授業で扱っており、それらに関する中国国内の状況はもちろんのこと、中国と比較して、他国ではどのような取り組みをしているのかについても紹介されました。
私が履修している授業はどれも、授業中に生徒と先生が積極的にコミュニケーションをとっており、ディベートやプロジェクトの発表などをする機会もあり、私がこれまでに受講してきた日本の大学の授業とは、全く雰囲気が異なると感じました。日本と比較して、中国では、先生と生徒の心理的距離が近いと感じることが多々あります。実際に中国人学生と一緒に授業を受けることではじめて、このような新たな気づきを得ることができました。
中国各地の視察
4月4日から7日までは清明節という連休がありました。この連休期間を利用して、中国の湖北省にある武漢市を視察するために、訪れました。4月3日の夜に北京から出発し、火车という汽車に約12時間乗って、4日の午前中にようやく武漢に到着しました。
武漢市は、長江が流れており、北京とはまた違った都市の雰囲気を感じることができました。また、中国は非常に広い国土を有しているため、地域ごとに特色のある料理があり、味つけも全く異なります。武漢は、热干面という麺料理が非常に有名で、北京でも食べることができますが、やはり本場のほうが非常に美味しかったです。さらに、黄鶴楼や租界地など、歴史を感じられる場所も多くありました。

写真は、夜のライトアップされた黄鶴楼です。黄鶴楼は唐の時代に、李白や白居易などが訪れ、詩を詠んだ有名な場所です。特に、李白の詩は有名で、私たちにとっても馴染み深いと思います。
武漢市といえば、コロナウイルスの発生源の地と言われていますが、実際に訪れてみるとその印象は一変しました。百聞は一見に如かずというように、実際に訪れ、自分の目で見てみることは、非常に大切だと改めて感じました。5月には、また労働節という連休があるので、様々な場所へ行き、今後もさらに見聞を広めていきたいです。

写真2:雍和宫(The Lama Temple)という北京で最大規模のチベット仏教寺院へ行きました。写真は、その寺院の中にある最も大きな仏像です。