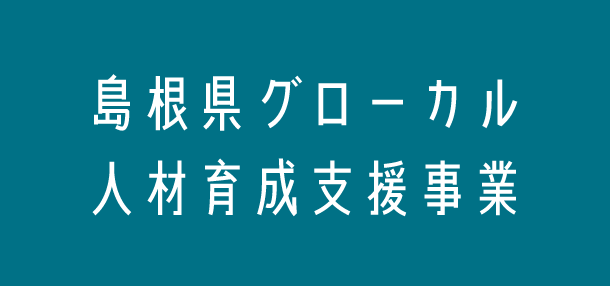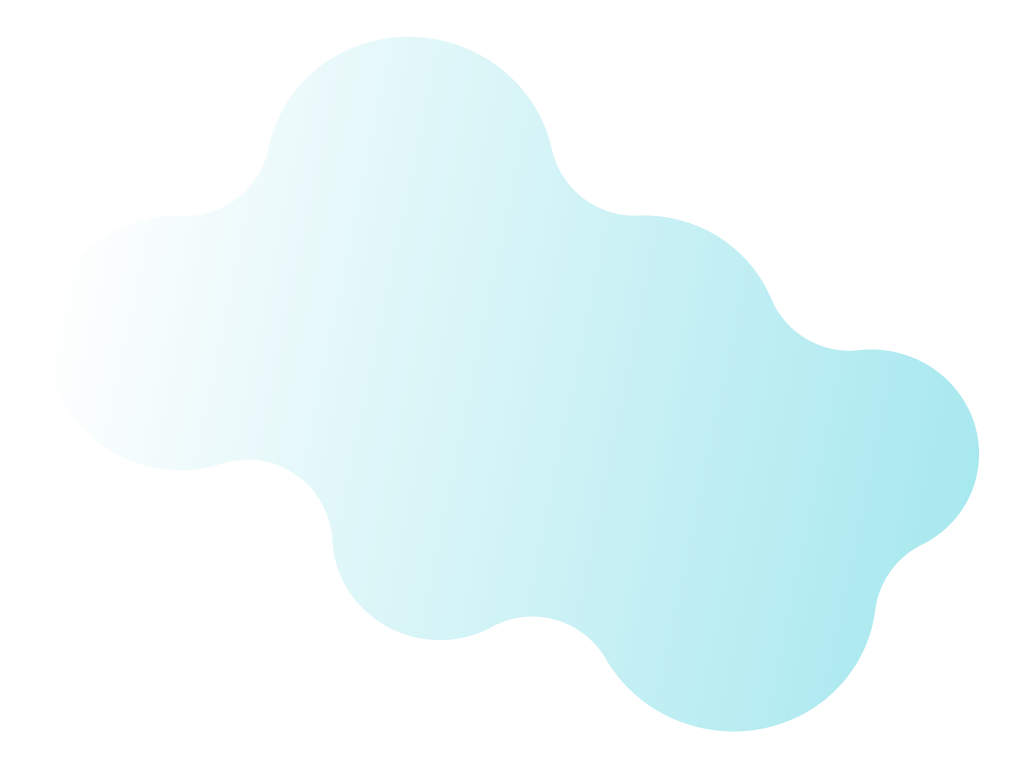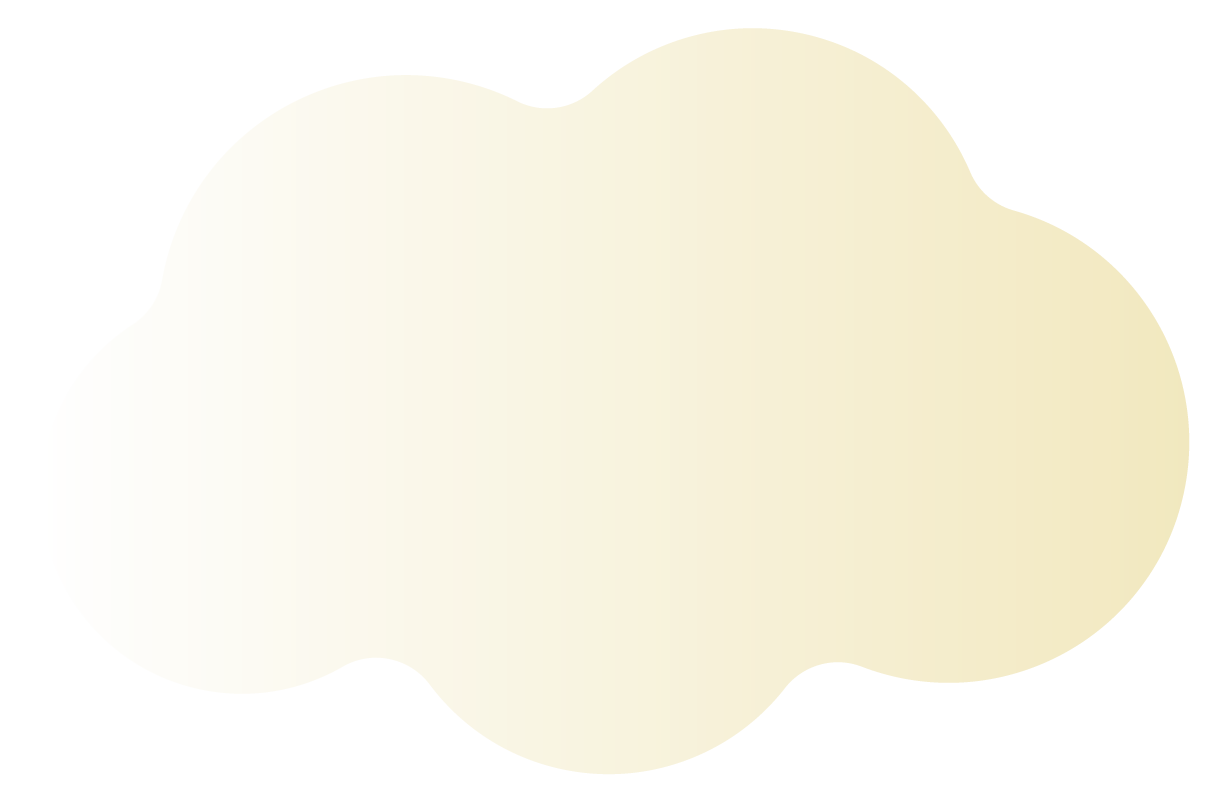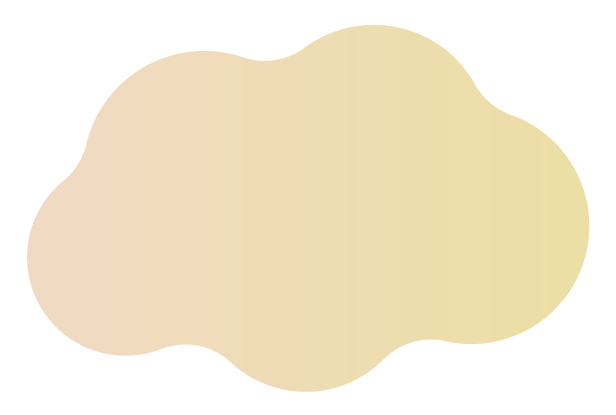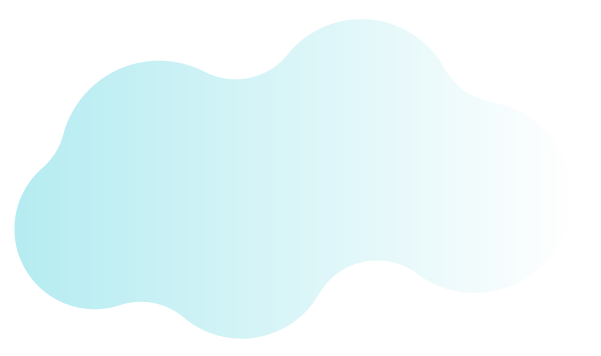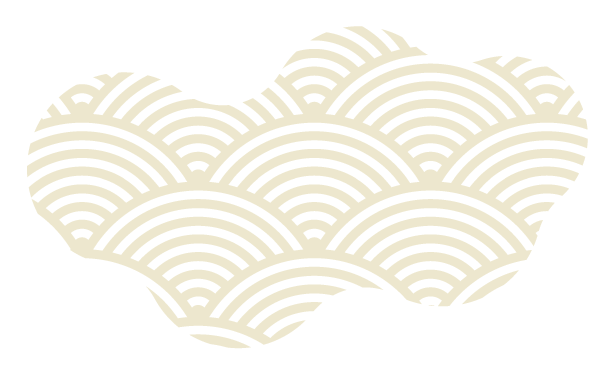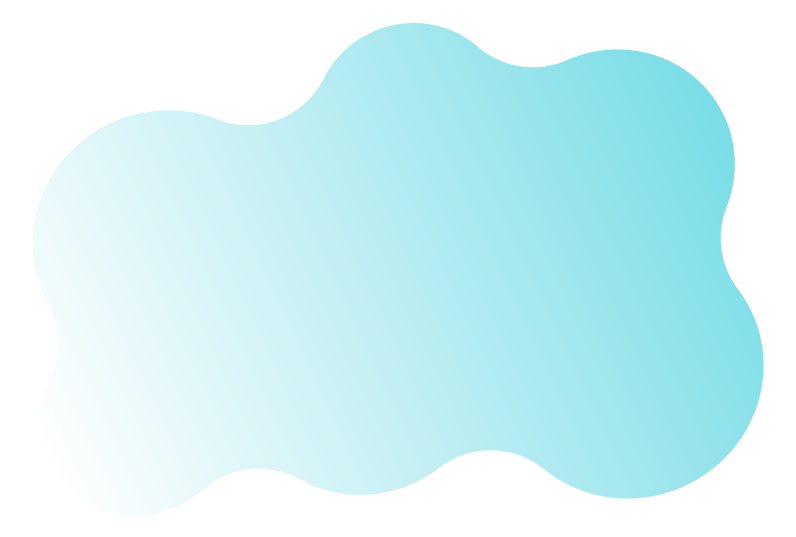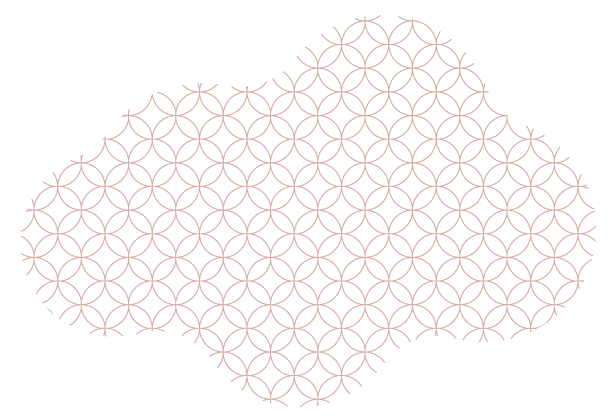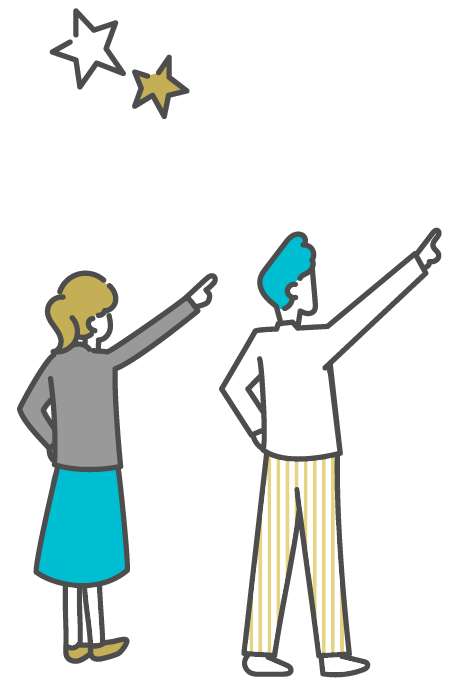第2回目 10月の活動 テストや留学生との交流
今月は中間試験があり、環境、建設材料学、水理学のテストを受けました。全てインドネシア語だったのでを理解するのは厳しかったのですが、専門用語を覚える良い機会になりました。
また、日本語学科の「日本のお辞儀と挨拶」という講義に参加しました。インドネシア語学科の日本人学生による授業で、インドネシアと日本の礼儀の違いを改めて学ぶことができました。
![20231108110122210060b3bdf[1]](/images/original/20240306161052508e0df67a3.jpeg)
写真:日本人学生による日本の文化紹介の授業の様子
現在の私のインドネシア語レベルは日々の生活や大学生との日常会話を理解する程度です。
この先のボランティア活動に向け、インドネシア人の前で何かを「教える」ことができるように、まずは大学の中でプレゼンや日本学科を含む学生主催の講義に積極的に参加していくことが課題です。
また、留学生協会(留学生のサポートに携わる学生によるグループ)の会議に参加し、「英語またはインドネシア語が得意ではない学生とどのようにコミュニケーションをとるか」という質問があがった際、日本人がその例として用いられました。
他国の留学生と比較すると宗教や言語(イスラム教徒の多くはアラビア語を学ぶ)の点で日本との共通点が少ないと捉えた可能性もありますが、日本に対して英語力が低いとイメージがあるようでした。
2023年に入学した留学生のためのオリエンテーションが行われました。西アジアやアフリカ出身の学生が多く、今年は日本の他にイエメン、マダガスカル、ナイジェリア、スーダン、東ティモール、サウジアラビア、アフガニスタン、シリアからの学生がいました。
マカッサルでの生活で注意することや出入国に関する内容を教えてもらい、短い休憩時には手遊びをして他の学生と交流を深めました。
![20231108110132658301be0d1[1]](/images/original/202403061610379179f9a94bd.jpg)
写真:マダガスカル(右2人)と東ティモール学生(左から2人目)との様子
今年は昨年に比べ乾季が長く続いているため、10月下旬は水不足が原因で計画的停電が実施されています。ほぼ毎日3〜4時間ほど停電が起こります。停電中はクーラーが使えないので時々休講になることもあります。雨季に入ればこの心配はなくなりますが、発電と水が密接な関係であることを痛感する月でした。
来月は、プレゼンテーションを含め、インドネシア人に「教える」という行為ができるようインドネシア語の上達を目指していきたいです。
また、日本が他国からどのようなイメージを持たれているのかを一年を通し確認していきます。歴史やタブー、相手からの印象を知っておくことで、接し方を見直すことができ、この延長線上には互いの調和の維持があると感じました。
![202311081101410177bded13e[1]](/images/original/202403061610247519dbf18c9.jpeg)
写真:メインキャンパス付近でのとあるデモの様子