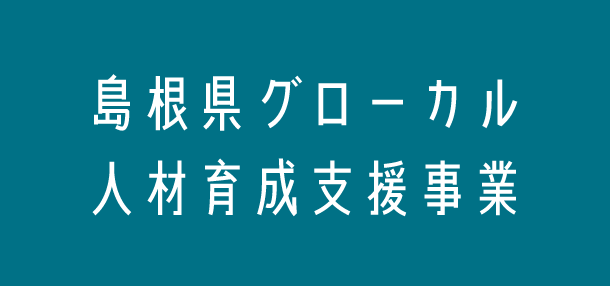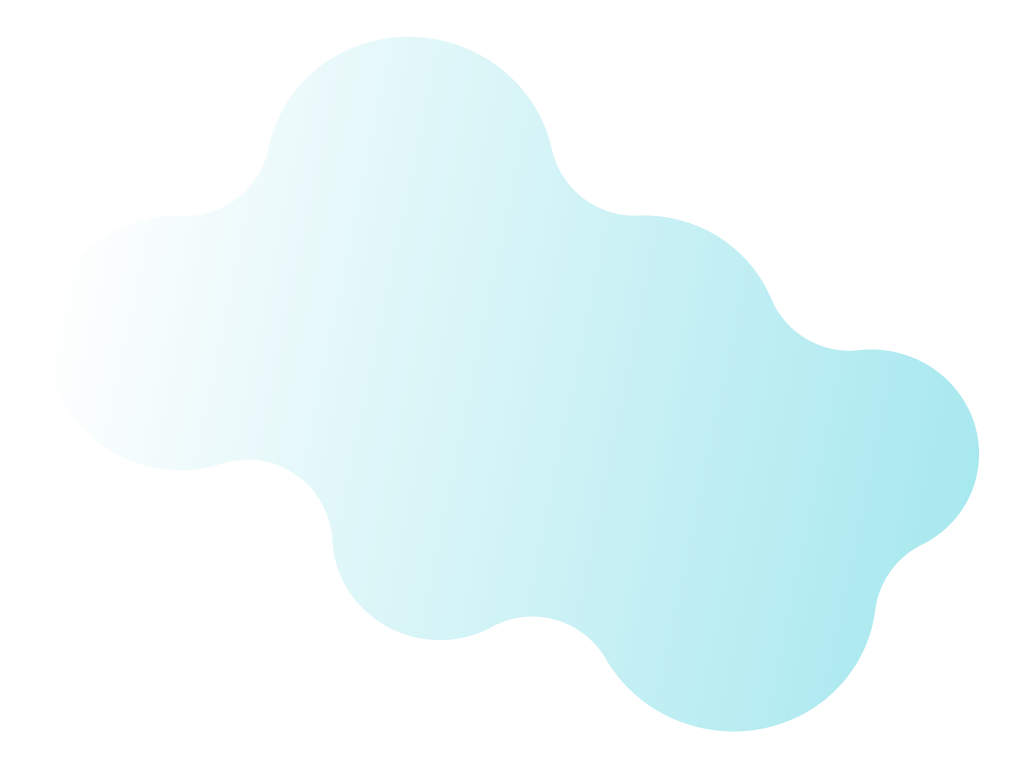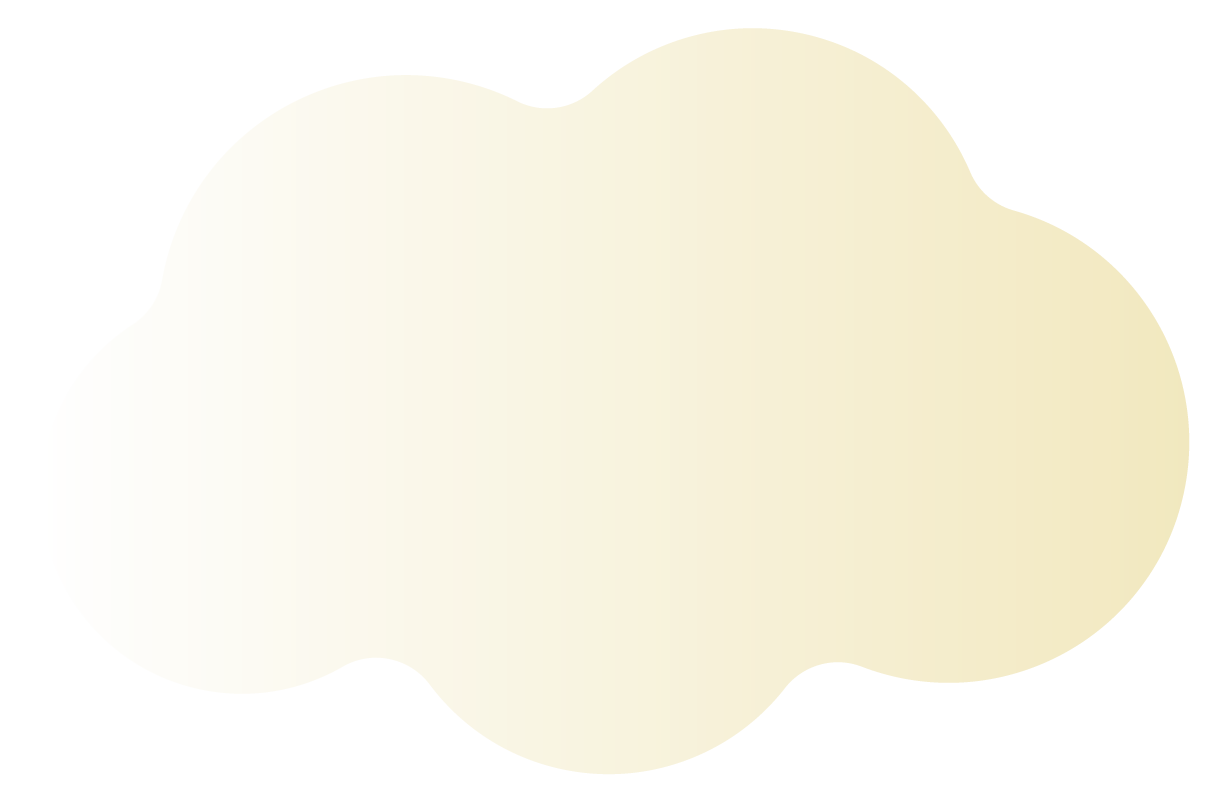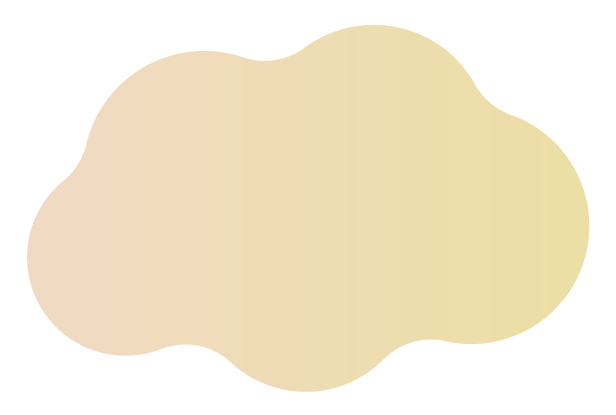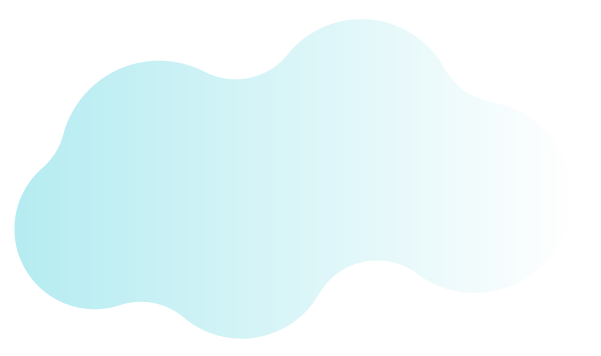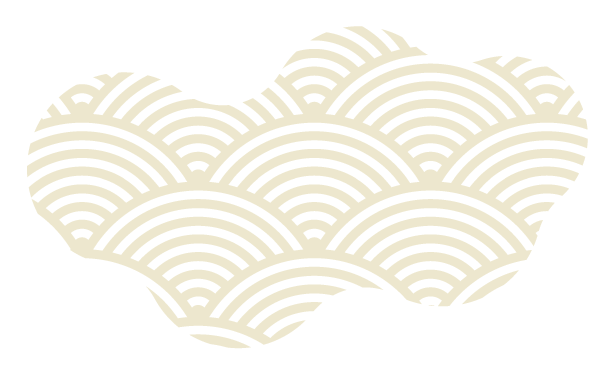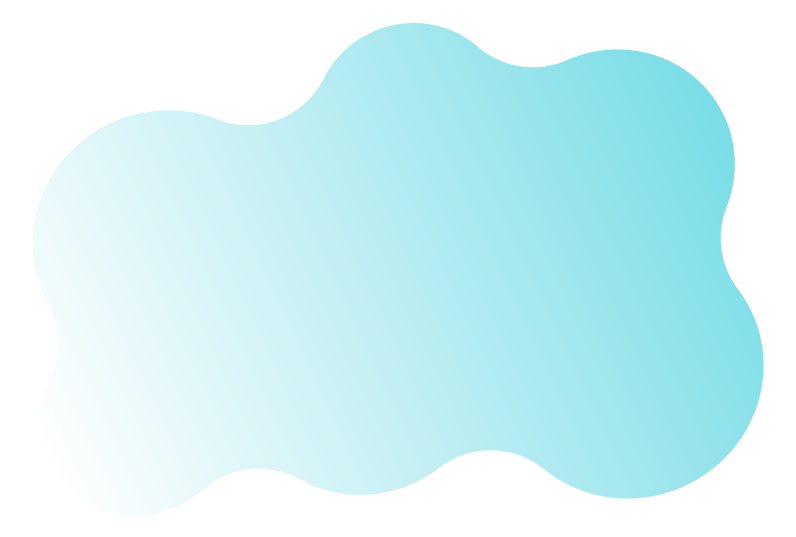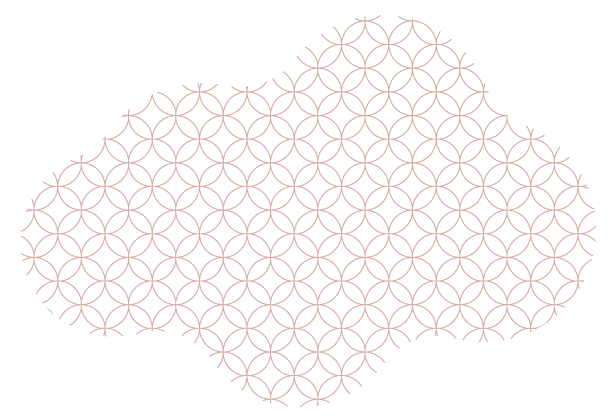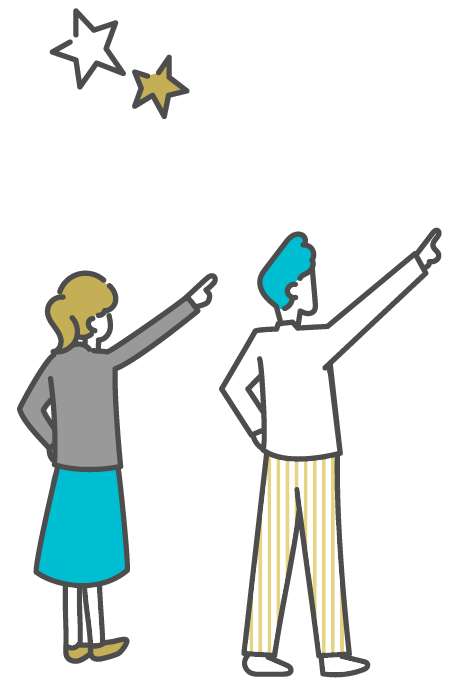第8回目 4月の活動 1ヵ月のラマダンとレバラン(断食明け大祭)
3月上旬から4月にかけて行われた断食に参加しました。
初めの1週間目は、水も飲むことができないので、一日中集中力が働かず、少しの移動にもとても疲れを感じました。街中も朝や昼は閑散とし、周辺のコンビニも閉まっており、モールなども人の数が極端に少ない状態でした。
2週間目以降では、日中の断食に慣れ始め、辛さは薄れました。太陽が昇る前の朝食を逃すと、1日のエネルギーが足りないため、毎日4時に起きて朝食を食べた後、再び眠るというスタイルです。学校の授業時間も、通常より30分遅く始まり、1時間半早く終わります。
断食が明け前日の夜は、ピンランという地域で過ごしたのですが、町中で断食終了を祝うために屋台が並び、道路にはトラックの上で太鼓を叩く人たちを多く見かけることができました。それは夜中まで続きます。

写真1:パトロールと呼ばれる断食明けを祝う人々
断食明け当日は、早朝からムスリムの人々はモスクへ向かいます。演説を聞いたのち、1年間の自分の行いを振り返り「Mohon maaf.(申し訳ありません。)」と自分の過ちを親戚や友達に謝り、また感謝を伝えます。そして、まるで正月とクリスマスとお盆、GWが一気に来るような1週間ほどの休みがあり、多くの人が自分の地元で家族と過ごします。

写真2:とある日の断食後の料理
期間中の大まかなルールは、日の出から日の入りまで飲食や喫煙が禁止で、他人に対して怒ることを控え、貧しい人に優しくするようにとも言われています。しかし断食へは、体調が悪い人や妊婦さん、高齢の方の参加する必要はありません。断食するかは自分の選択で決めることができます。
今回最後まで断食に参加できたのは、友人や先生など皆参加しているからだと感じました。
「なぜ辛い思いをしてまで、断食をするのか。」それは信仰心を深めたり、ムスリムの中で団結を強めたりするためだと言われています。日本の文化からすると異文化で理解するのは難しいです。しかし、文化に効率性を求めないように、言語が時々規則性から外れるように、ここでは当たり前のようです。現地の方々と同じような生活を体験し、ご飯が食べられないことで日中の体のコンディションは落ちますが、日が経てば精神的には慣れました。
マカッサル市内運動イベントへの参加
マカッサル市内では、いくつかのジョギングエリアが存在します。週末はそこで運動イベントが開催されます。1時間半ほど、50人程の参加者とともに踊ります。インドネシアでは多くの人がバイクや車での移動のため国民の運動不足が懸念されていますが、このように健康と向き合うイベントが定期的に開催されているようです。

写真3:運動イベントの様子
ムスリム学校の先生にお会いする機会がありました。その学校では、英語の他に日本語の授業を行なっています。次回はこの学校の授業に参加しようと考えています。
また、6月に「犠牲祭」と呼ばれる宗教イベントが開催される予定なので、そこにも参加する予定です。まだまだインドネシア文化を知っていきたいです。