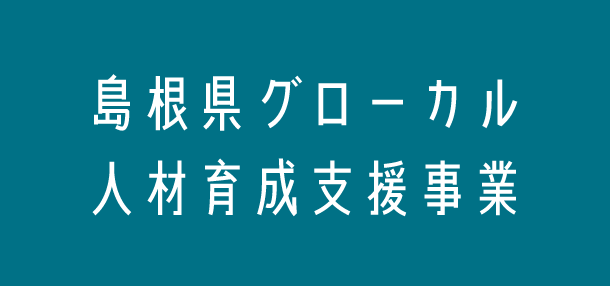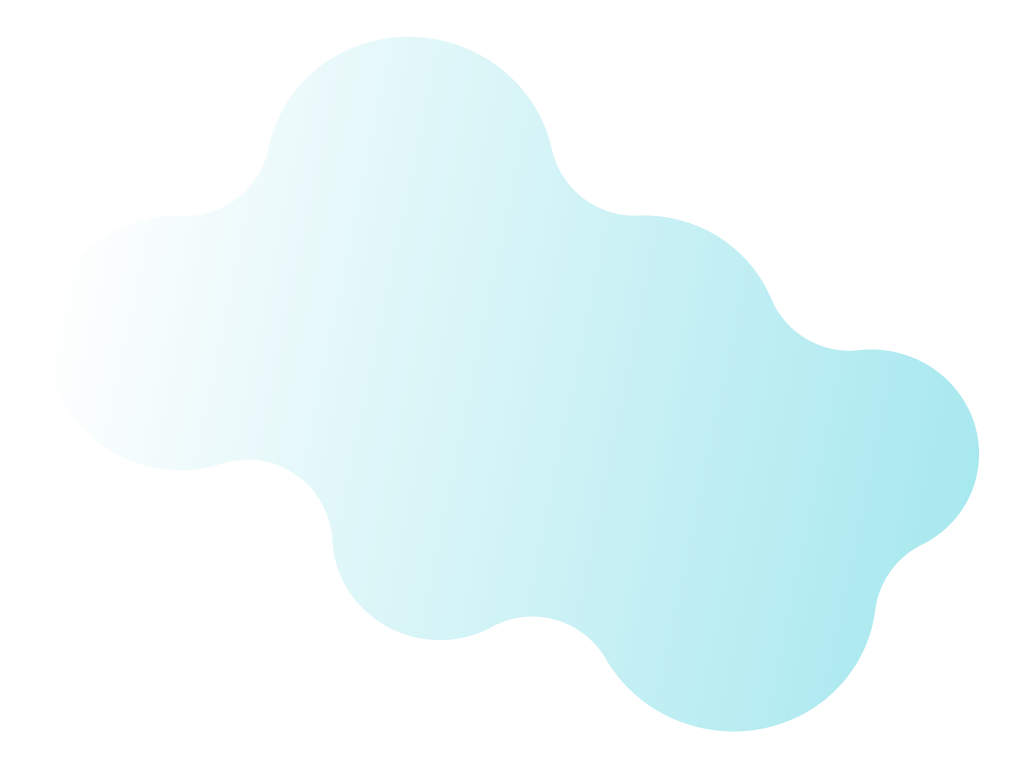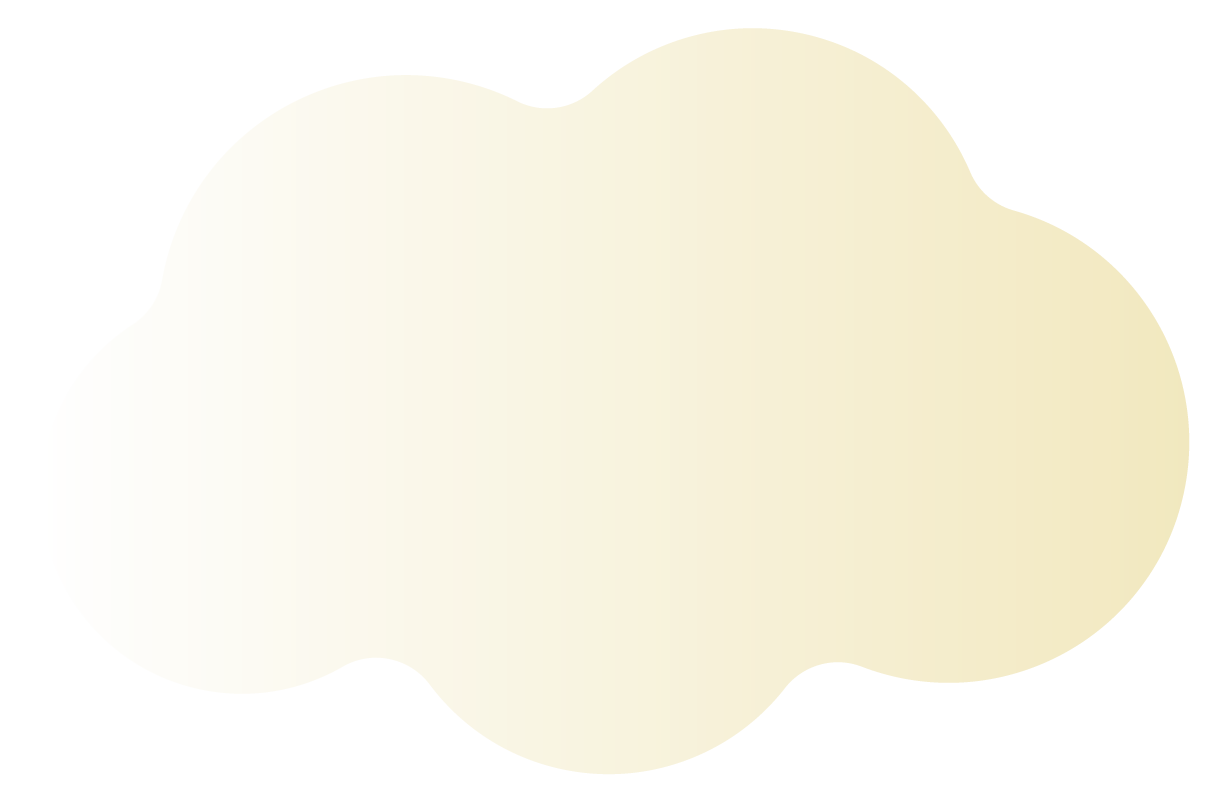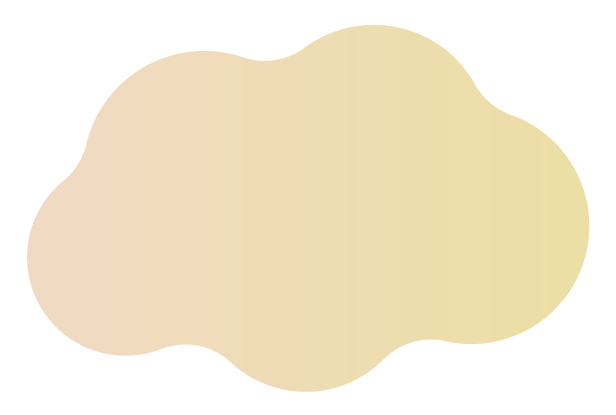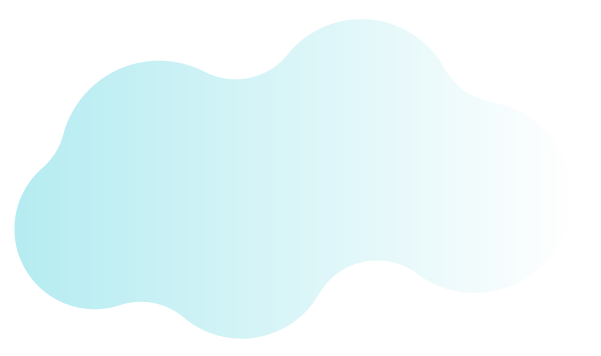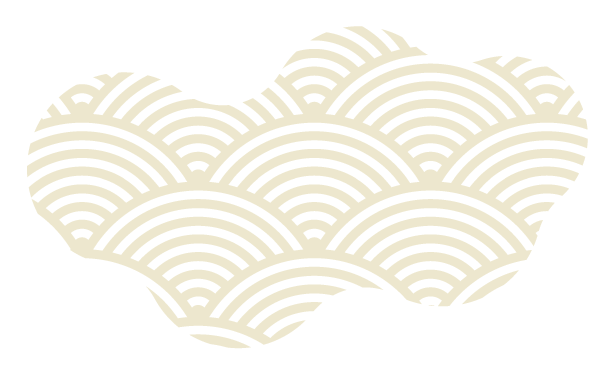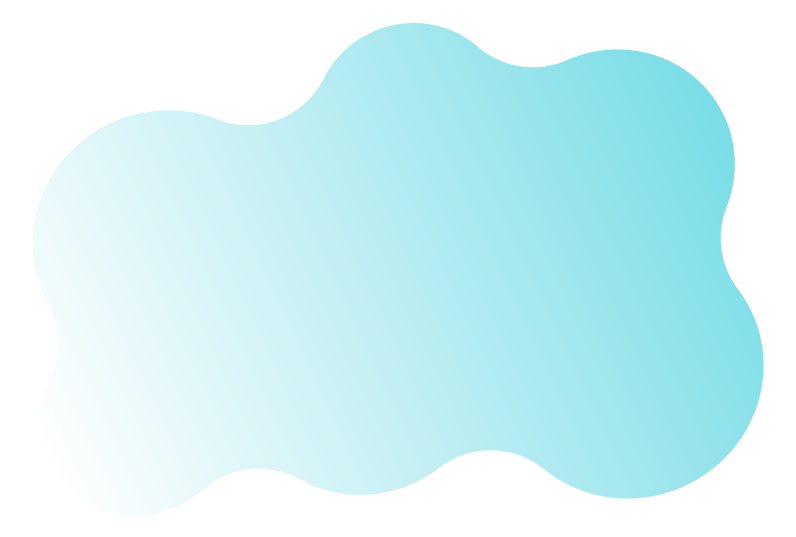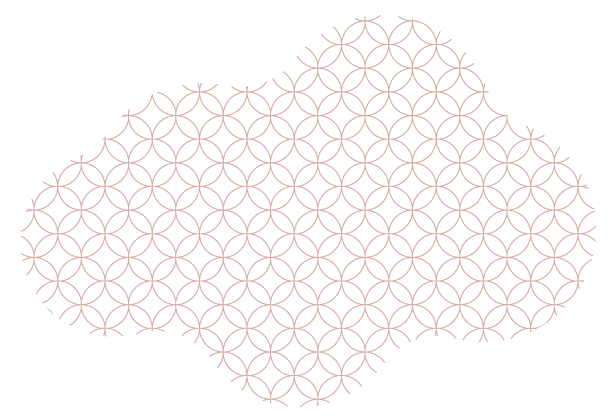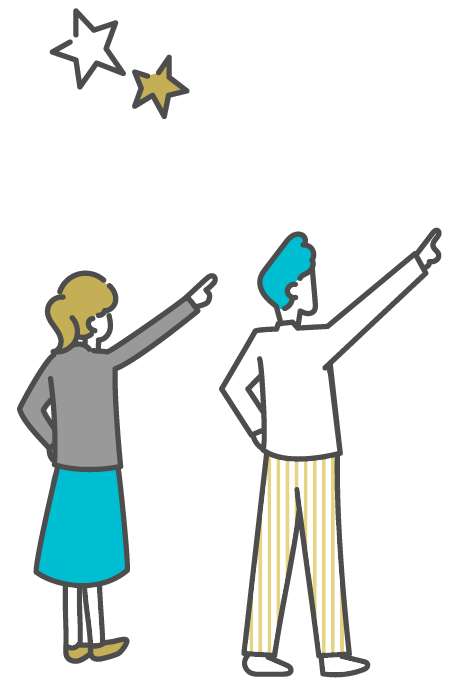第5回目 1月の活動 取材活動と日本食晩餐会の開催
現地の雰囲気を味わうために、正月はフローニンゲンで過ごすことにしました。正月に向けて部屋でぬくぬくしていると日本の外務省からメールが届きました。曰く、「オランダ全土で花火の打ち上げは全面的に禁止されているが、正月前後の数日間は市民はお構いなしに打ち上げるので気をつけてください」とのことでした。以前から教授に「オランダ人はルールに厳格だ」と聞いてましたが、どうやら正月は例外のようです。
今月の活動内容はソフトウェアの開発を進める傍ら、先月に引き続き企業・団体に取材をしてきました。私の留学テーマは社会問題の解決で、その主体は自治体・自治体をサポートする営利企業・NPOに大きく分類できます。今月はある企業とNPOにそれぞれ話を聞いてきました。
自治体/政府の調達をサポートする企業に取材
今回取材をしたのは、Sprout9の代表アンソニーさんです。アンソニーさんは内務省で政府調達の政策立案に携わりながら、Sprout9で政府/企業の調達に関する人材不足を解決するサービスを提供しています。このサービスの興味深い点は、高水準の時給で学生アルバイトを雇って育成し、長期間自治体や企業の支援をすることで卒業後はそのまま就職に繋げることができる点です。その結果、より長期的に人材不足の問題を解決できるようになります。オランダ政府も調達人材の育成プログラムを実施しているようなのですが、Sprout9は市場の力をうまく使ってより大規模にこの問題を解決しようとしておりとても参考になりました。
他にも、自治体での知識集積/人事に関する理論やオランダでの動向、起業初期における実務的なアドバイスなど様々な話を聞くことができました。

(写真1_アンソニーさんと)
住宅問題に取り組む団体に取材
次に取材をしたのは、住宅支援を通じて貧困層の生活向上を目指す非営利団体 Habitat for Humanity (オランダ支部)のエヴァさんです。Habitat for Humanityは世界約70カ国以上で活動を行う国際的な団体です。活動場所だけでなく実施プログラムの幅も広く、住宅の建設・運営から自然災害後の復興支援、地域のコミュニティ支援やマイクロファイナンスまで行っています。
特に聞きたかった点は、NPOとしての運営方法です。企業とも自治体とも異なり大部分の資金が寄付で賄われていますが、その支援者とのコミュニケーション方法に興味を持っていました。
いくつかの施策を聞きましたが、一番重要だと感じたのは、社会的な変化を体系的に計画し、評価するためのフレームワークであるチェンジ理論(Theory of Change)を参考に、団体の意義・長期的方針をまず伝え、寄付金がどのように使われて社会への影響力に変わったかを算出して提示していることです。具体的には、€1ごとのコスト/成果を算出することで、例えば「100ユーロの寄付で○○が実現できる」という説明ができるようです。オランダでは「寄付が適切に使われているかどうか」に対する関心が非常に高く、一部の非営利団体での不正が問題視されたこともあり、寄付の透明性と効率性を示すことが重要になっているとのことでした。

(写真2_エヴァさんと)
日本食晩餐会の開催
日本文化を広めるために、寮の友人を招いて日本食を作ることにしました。驚いたのが、友人のほとんど全員が家で一度は寿司を作ったことがあることです。それほどに日本食への興味があるようで気付けば参加者は10人を超えていました。
一人で10人以上を用意するのは大変だとな思っていたところ、日本でシェフをやっている友人が偶然ヨーロッパに来ており、ダメもとで手伝いを頼むとなんと快諾してくれました。その結果、ポテトサラダ・だし巻き卵、唐揚げ・鍋(+締めの雑炊)という豪華な晩餐になりました。
面白かったのがドイツ人の友人はポテサラ、スペイン人の友人は唐揚げ、と国ごとに気に入る料理が違っていたことです。だし巻き卵は押し並べて人気でした。

(写真3_使った食材)

(写真4_晩餐)
企業・団体へのインタビューの段取り
当初の計画に加えて、(先月レポートに登場した)オランダ自治体協会(VNG)および「Signalen」というOSS(オープンソースソフトウェア)の管理者である方に取材ができることになりました。
OSSを使って自治体の効率化サービスを提供している例は少なく、そのプロジェクトの背景や運営方法など私の活動にも直結する面白いことが聞けそうで楽しみです。