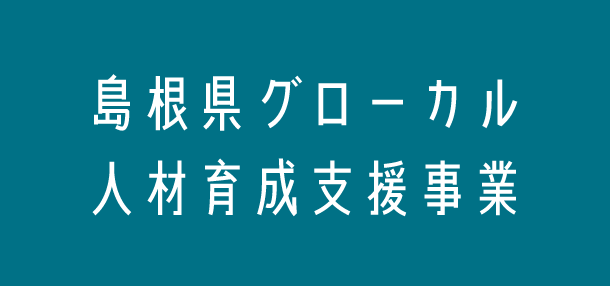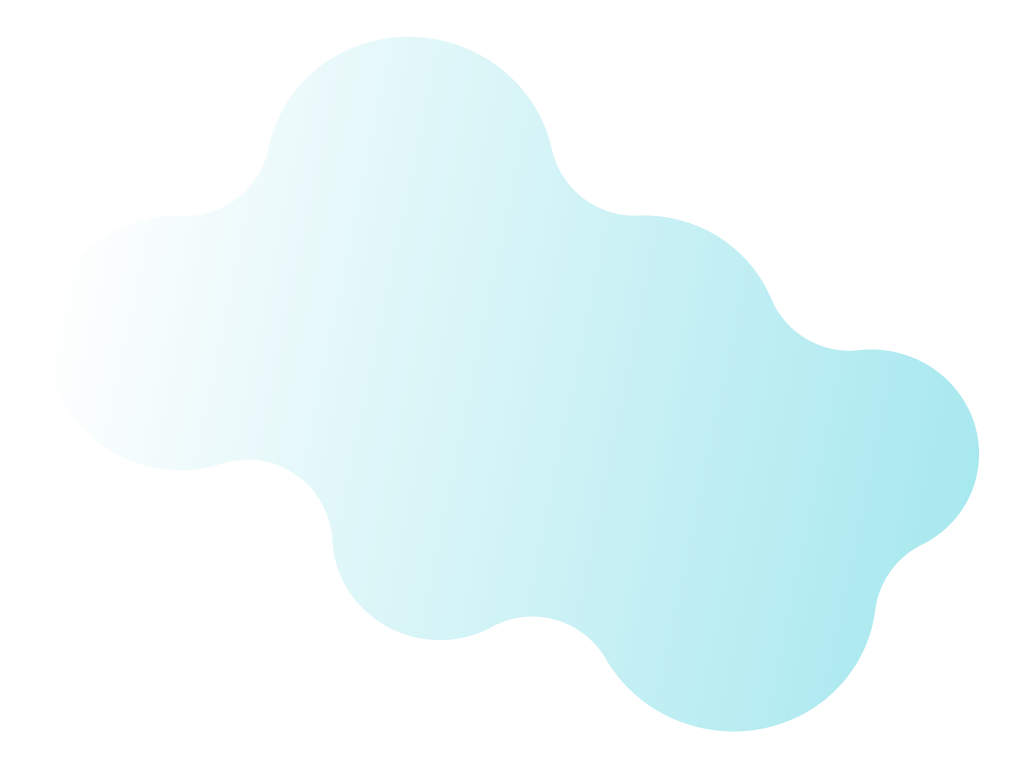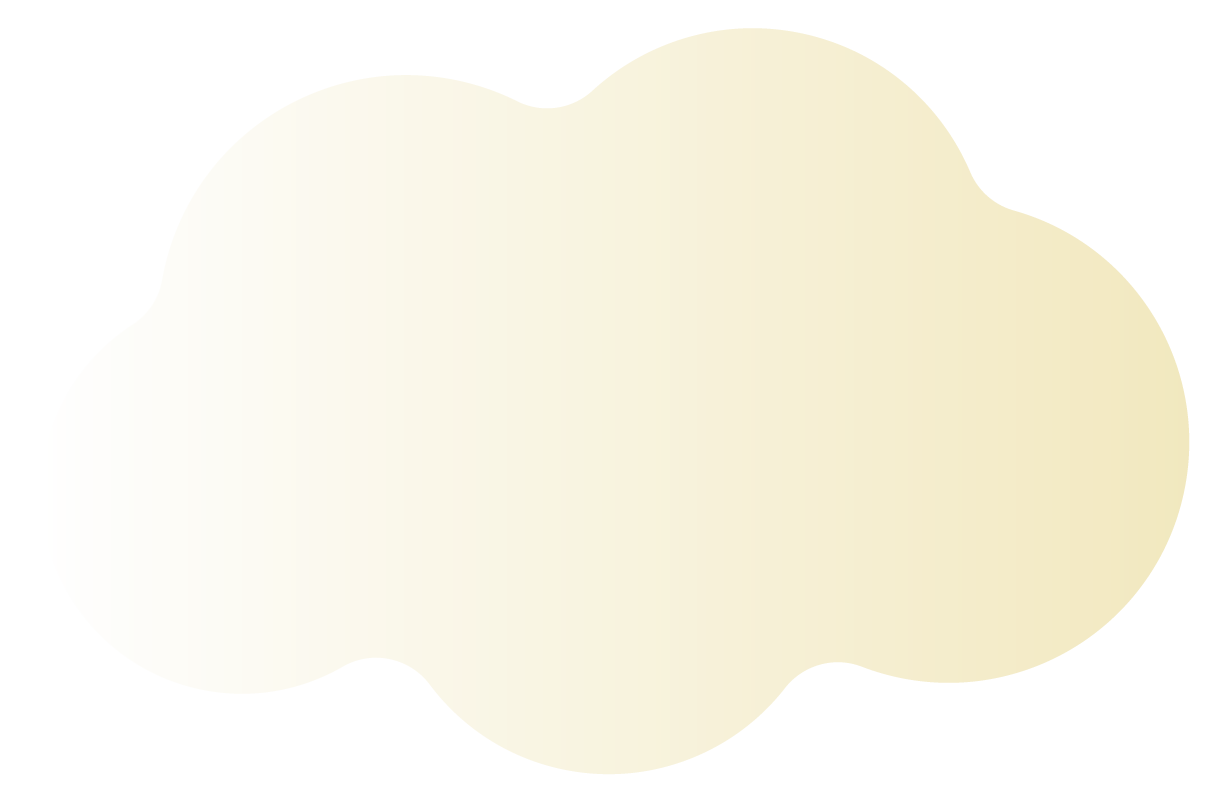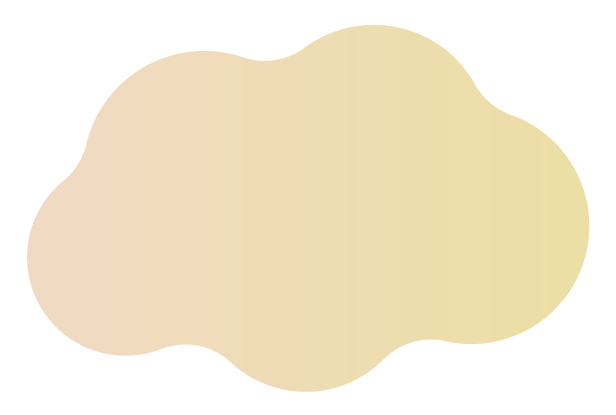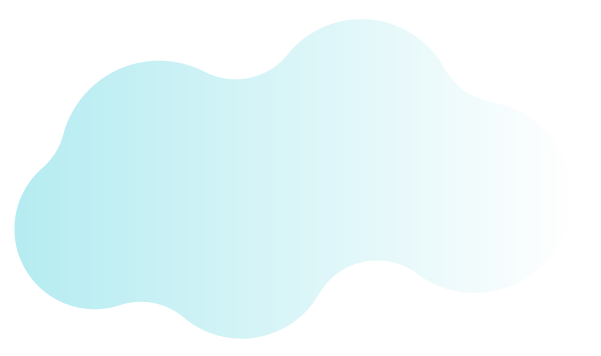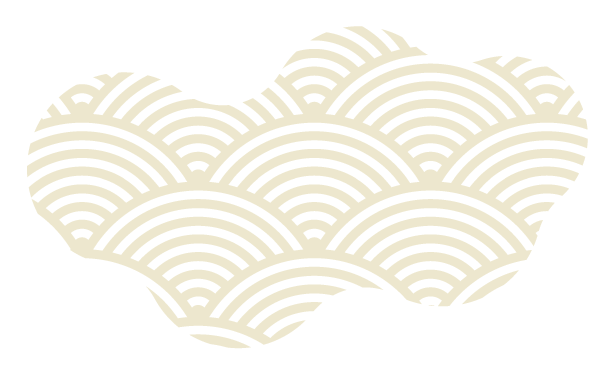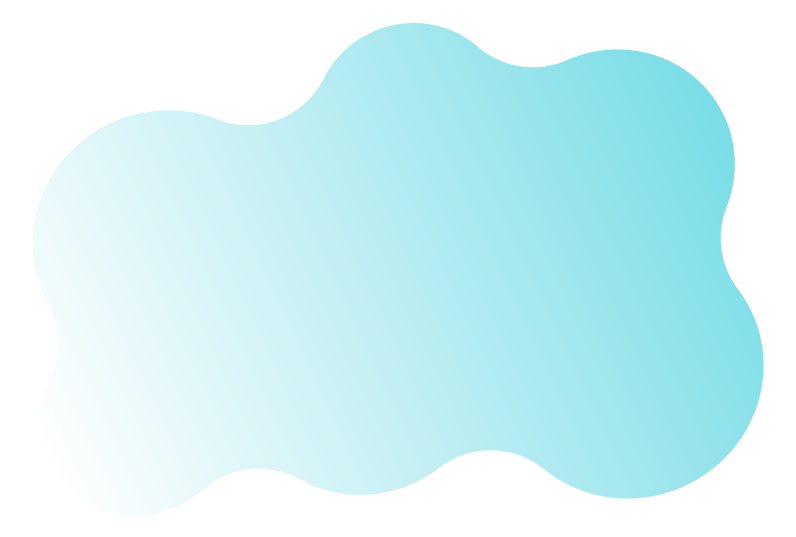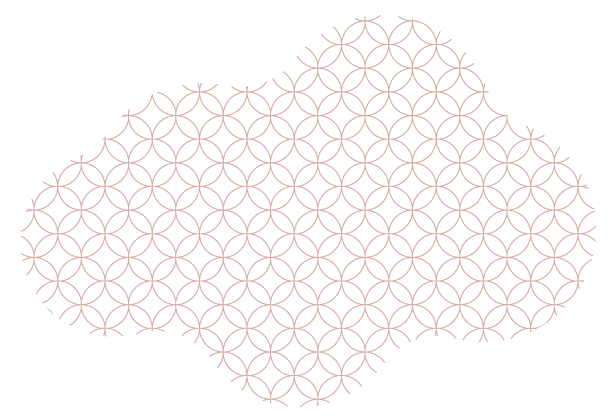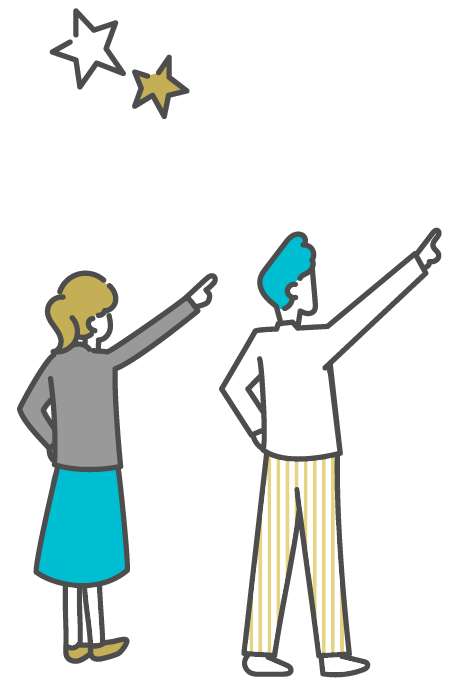第2回目 10月の活動 自治体・企業へのインタビュー
大学のテスト
先月、体調を崩さないようにする、と言っておきながら1週間ほど重い風邪にかかって寝込んでいました。
異国で重い風邪にかかった時の寂しさたるや、なかなかのものでしたが、友人達に助けてもらい今ではすっかり回復しています。風邪の対策は国ごと人ごとに色々あるようで、ドイツ人の友人は、生姜を生でむしゃむしゃ食べており、驚かされました。
そうこうしていると、前学期のテストがやってきました。今学期に主に履修しているのは、行動経済学、組織内のチームワークについての講義です。どちらも理論の応用に特化した講義であり、今ままで理論を中心に学んでいた自分にとっては新鮮味があります。
これからオランダでは一層冬の厳しさが増すので、体調には気をつけようと思います。

(画像1. 謎の緑の光が輝く夜の中央キャンパス。テスト期間中は図書館が24時まで空いています。)

(画像2. 曇り模様が続くZernikeキャンパス)
自治体・企業へのインタビュー
今後自分の活動を上げていくにあたり、改めて全体像を書いておこうと思います。
私の長年のモチベーションは「社会問題をビジネスでどう解決するか」であり、そのために幾つかのソフトウェアを開発しています。そして、この留学では「どのように、災害用備蓄の不足や大気汚染などの"社会的ジレンマ"を解決していくのか」というのが大きなテーマです。
"社会的ジレンマ"とは、各企業や個人が互いに少ずつ協力すれば社会全体が良くなるにも関わらず、身勝手に行動をしたために社会全体が不利益を被る状態を言います。小さくはゴミのポイ捨て問題から、大きくは地球温暖化までもが社会的ジレンマの問題といえます。
その問題を解決する主体の多くは政府/自治体になりますが、問題が複雑になればなるほど、民間の技術や知識が必要になります。しかし、民間側に頼み切りの構図になると、癒着や発注側の知識/管理不足による立場逆転など別の問題が起こり得ます。なので、複雑な社会問題の解決には、両者の適切な関係、そしてそのための制度や取り組みが必要不可欠です。私の目的は、これらを含めた歴史的また現在における、社会的ジレンマの解決法を探ることにあります。
今回、自治体関係者・政府の調達(procurement)をサポートする企業の代表の方に話を聞くことができました。特に興味深いと感じたのは以下の3点です。
- EU内では、ある国での政府調達の入札には原則どの国の企業でも参加できるように、EUレベルでの条約で定められている
- オランダ国内では2年ほど前、政府と大企業が持続可能な社会を目指す調達に関するマニフェストに調印した
- 政府調達は、よほど専門性が高い場合を除き、知識と経験のある職員が主に対応する
1. に関しては、欧州経済領域では人、サービス、資本の移動の自由の原則があるので当たり前かと思われるかもしれませんが、競争原理が働くための制度がしっかり整備されている点が興味深いと思いました。具体的には、入札の電子化と透明化です。EU全体でTED(Tenders Electronic Daily)というシステムが運用されており、各国の政府調達システム(オランダならTenderNed)と連携されています。そこでは、詳細のプロセスや評価基準が細かく明示されており、不満を持った企業による訴訟も頻繁に行われているとのことです。日本との比較では、この点が大きな違いの一つではないかと考えています。
2. に関しては、社会的ジレンマの解決につながる手であり、ヨーロッパ議会における環境政党の議席数の拡大とも関係しているように思われます。2~3年前までは、政府調達の評価基準は高品質で低価格であることが一番だったが、それがこの数年で大きく変わったようです。
3. に関しては、特にインフラ・防衛・ITおよびサイバー関連では調達チームも大きくなり、外部から専門家を雇う場合も増えるとのことでした。
他にも、数年前までは防衛費を減らす議論もあったが現在は議論の余地はなく、ヨーロッパ全体で供給不足の傾向にある話や、オランダは比較的他国からの調達が多く、戦争や感染症のリスクを考えるとサプライチェーンの確保が大きな課題であるなど非常に興味深い話を多く聞くことができました。
今後は、調達をこえて自治体全体での知識の蓄積や人材育成に関する取り組みを中心にまずは調べていく予定です。合わせて、世界的にも特異な自転車中心の街づくりの成立過程も探っていこうと思います。