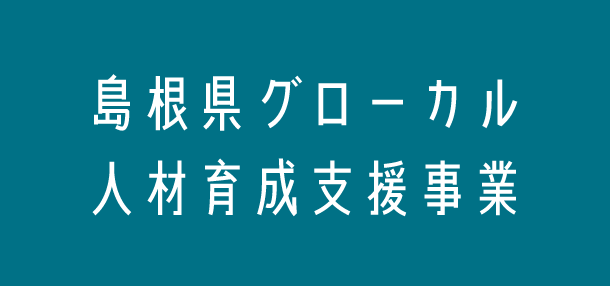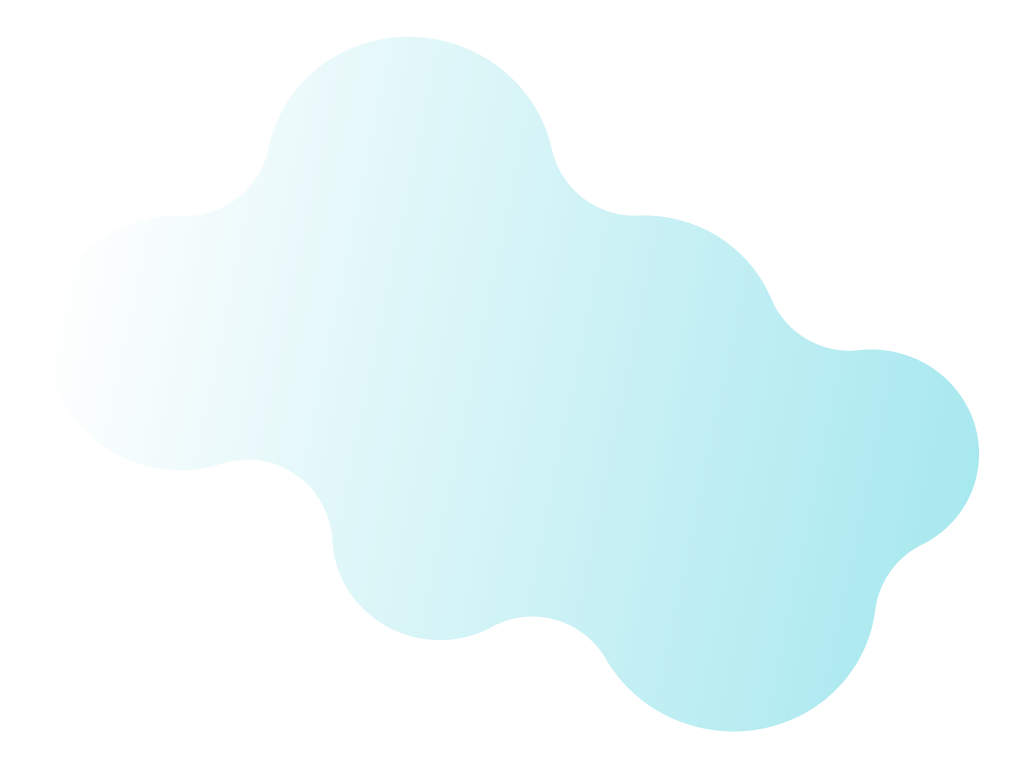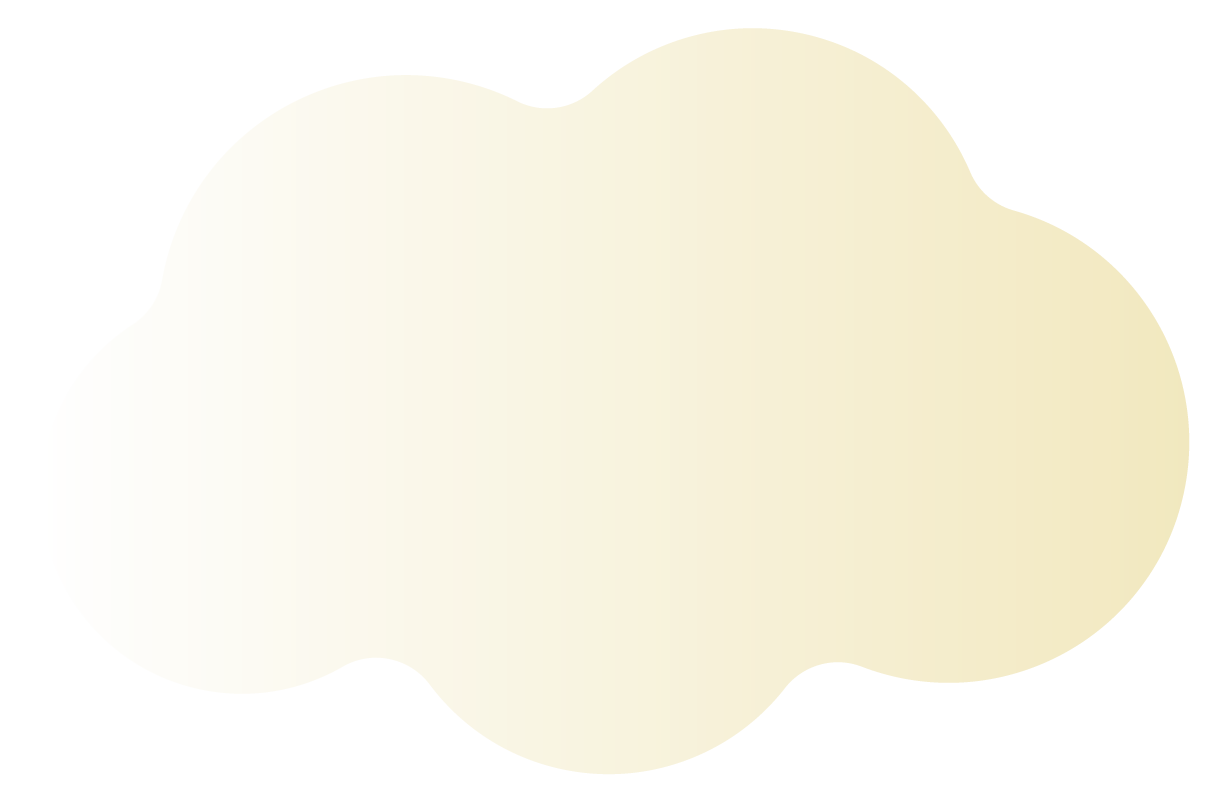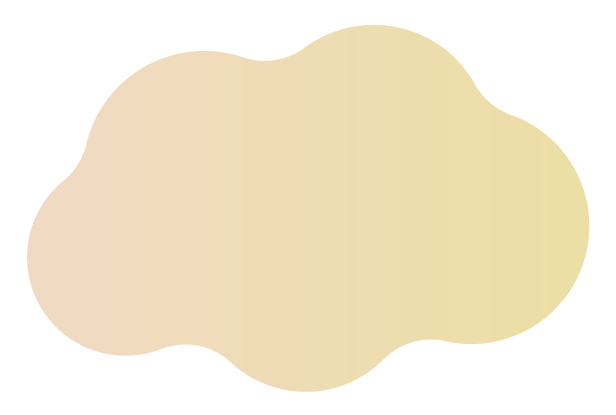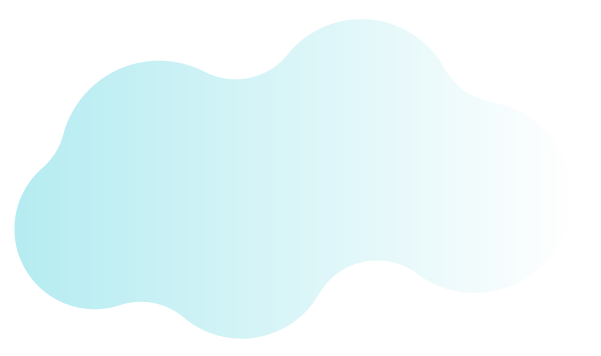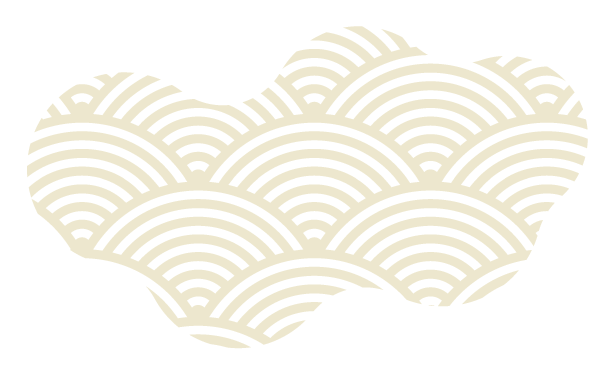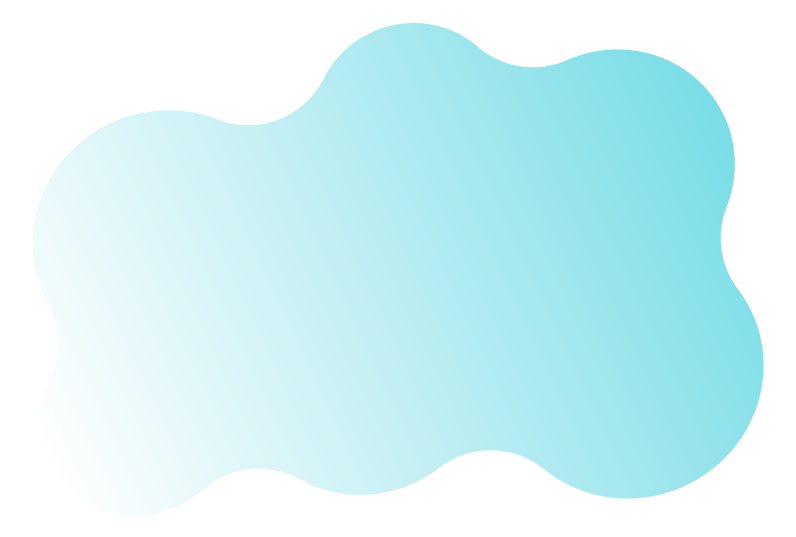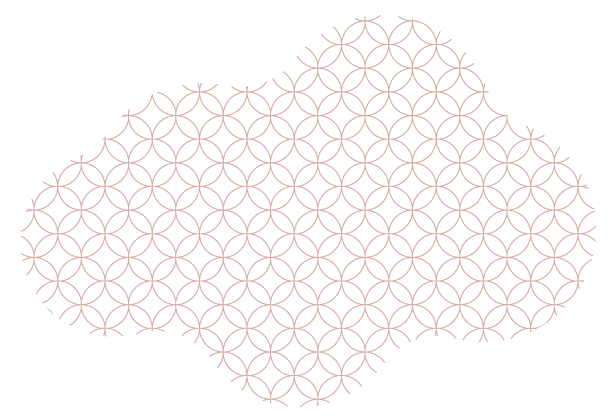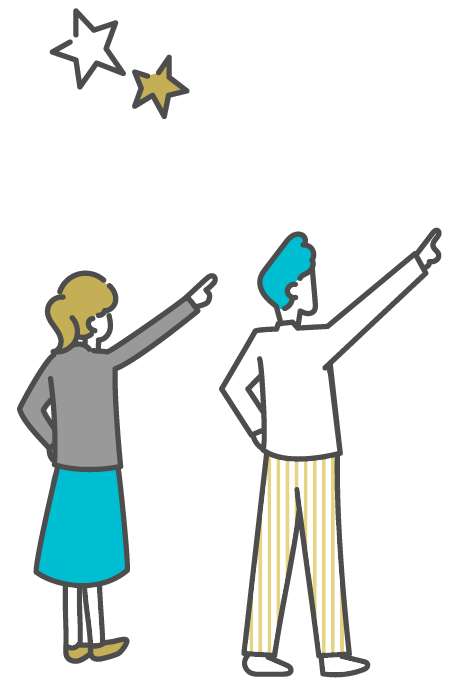第5回目 7月の活動 ホームステイとBig Shabbat Dinnerへの参加
シャバットディナーに参加して
私はクラクフのJewish Community Center (JCC Krakow) にてユダヤ人コミュニティのボランティア活動を始めました。ユダヤ人という言葉は歴史の授業の中で触れたことはありましたが、実際にどのようにユダヤ人の文化やアイデンティティが今日に至るまで受け継がれているのかを知る機会はこれまでありませんでした。クラクフはホロコースト(ナチス・ドイツによってなされた、600万人のユダヤ人虐殺)の歴史を抱える地でもあります。この地でユダヤ人コミュニティがどのように暮らし、文化を継承しているのかを直接学びたいと思い、コミュニティに連絡を取り、ボランティアとして活動することが決まりました。
初めての参加はJewish Culture Festival、という年に1度の大きな祭りでした。この期間中にはエルサレム、フランス、アメリカなど世界中からユダヤ人が集まり、多様なイベントが開催されました。その中で私はBig Shabbat Dinner(ビッグシャバットディナー)の運営ボランティアに参加しました。

(写真1)Big Shabbat Dinnerの会場の様子です。
「Shabbat(シャバット)」とはユダヤ教における大切な安息日で、金曜日の日没から土曜日の日没までを神聖な時間として、家族やコミュニティとともに静かに過ごす伝統があります。通常は毎週金曜日の夜に、コミュニティセンターにて小規模の2部制で行われていますが、今回は特別に、世界各地から集まった約700名のゲストが一堂に会する大規模なディナーが開催されました。会場には高齢の方から小さなお子さんまで幅広い世代の方々が参加されており、世代を超えて一緒に食卓を囲む光景がとても印象的でした。
私はボランティアとしてゲストへの案内などの運営補助、お皿の準備、飲み物の補充、片付けなどを担当しました。ディナーの始まりには、ろうそくに火を灯してお祈りを捧げた後、ワインまたはぶどうジュースで乾杯をし、「ハラ」と呼ばれる編み込みパン(写真2)を皆で分け合ってから食事が始まります。ディナーの途中には、ゲストが歌を歌いながらグラスを掲げる場面もあり、会場全体が一体となって温かい空気に包まれていました。

(写真2)これが「ハラ」と呼ばれる編み込みパンです。
この経験を通じて、ユダヤ人コミュニティが単に宗教的なつながりだけではなく、歌や祈り、食事を通じて世代や国を超えた人々のつながりを生み出していることを学びました。
そして、長い歴史の中でさまざまな背景を持ちながらも、今を生きる人たちが、自分たちのアイデンティティを大切にしながら、温かいつながりのあるコミュニティを築いている姿に、心を動かされました。
ポーランドの田舎Bukownoホームスティ生活を体験
私はクラクフを少し離れて、ポーランドの田舎町で約2週間ホームステイをしました。クラクフは第2の都市ということもあり、便利で都市的な暮らしができますが、私の留学の目的の一つに「地方創生をポーランドから学ぶ」というテーマがあります。だからこそ、地方に住む人たちのリアルな暮らしや教育の現場に触れたいと思い、ご縁のあったご家庭でお世話になることにしました。
ホームステイさせていただいた家庭は、最寄りのお店まで歩くと1時間ほどかかる場所にあり、車での生活が必須でした。その分、緑が多く、自然が身近にある美しい町でした。滞在先では、庭でチェリーやリンゴ、ベリー、食べられる葉っぱなどを育てており、自給自足のような暮らしをしていました。私自身、庭で採れたものを洗わずにそのまま食べる経験はほとんどなかったため最初は驚きましたが、子どもたちが外で遊びながら庭の実をそのまま口に運ぶ姿を見て、自然と共に生きる暮らしの豊かさを感じました。
ポーランドの学校は、6月後半から9月まで夏休みです。また、子どもたちは日本のようにたくさんのドリルや作文の宿題はないそうです。なので、子どもたちは時間がたくさんあり、退屈しそうと思いました。しかし、この町の家庭はどこも庭が広く、庭にはブランコやトランポリンなどの遊具が置かれており、子どもたちはスマホやお金を使わなくても思い切り遊んで楽しめる環境がありました。
小学校や中学校の1学年10人程度の小規模というお話を聞きましたが、公園が町の中にいくつもあり、子どもたちが自由に遊べる場が確保されていることに驚きました。私自身、小学生の頃は徒歩圏内に公園がなく、室内で過ごすことが多かったため、自然の中で遊べる環境が子どもの成長にとって大切だと改めて感じました。
滞在した家庭には11歳、8歳、4歳の子どもがいて、私は家事の手伝いや子どもたちと遊ぶことに加え、庭でベリーを摘んで種を取る作業(写真3)、ガーデニングの手伝いもしました。普段は画面の前で過ごす時間が長い私にとって、大きな庭での作業は大変でしたが、とても良い時間になりました。

(写真3)自家製のジャムです。
このホームステイで特に印象的だったのはポーランドでは1日に4食の習慣があることです。まず朝食、正午頃に軽食、午後四時頃に温かい料理、午後8時ごろに軽食を食べるのが一般的です。この午後四時頃の食事が「obiad(オビアッド)」と呼ばれ、ポーランドの一日の中で最も大きな食事の時間となっています。その後の軽食はパンやサラダなど簡単なもので済ませる家庭が多いようです。初日は「なぜこの時間にご飯を食べるのだろう」と驚きましたが、これがポーランドの食文化であることを知り、生活のリズムに慣れていくことができました。また、お母さんが毎日ポーランドの伝統料理を作ってくださり、食卓の時間が毎日の楽しみになりました。(写真4,5)

(写真4)近くにはファストフードがないので毎日、手作り料理です。

(写真5)ポーランド料理を毎日食べられて大変幸せでした。
今月のまとめ
夏休みが始まった6月末の時点では、7月の予定がほとんど決まっておらず、不安や焦りを感じていました。しかし、ユダヤ人コミュニティのボランティア活動やホームステイを通して、ポーランドのより本質的な生活を体験でき、貴重な経験になりました。
ユダヤ人のボランティア活動は今後も毎週行われる予定なので、引き続き積極的に参加しながら、ユダヤ人コミュニティがどのように伝統や文化を継承しているのかについて学んでいきたいと思います。また、8月には私の家族や友人がクラクフを訪れてくれる予定で、その際にアウシュビッツ収容所を訪問する計画を立てています。留学を決める前からずっと訪れてみたいと思っていた場所なので、ようやく行けると思うとワクワクしています。
今回ホームステイさせていただいたご家庭の方は、学生時代はクラクフで暮らしていたそうですが、「人が多くて忙しい都会よりも、田舎のゆったりした生活のほうが自分には合っている」と感じて、最終的に田舎に戻ることを選んだと話してくれました。
私の島根県出身の友達にも、大学は県外に出て、就職のタイミングで地元に戻ってくる人はいますが、その理由としては「家族や友達がいるから」という声をよく聞きます。そういった中で、「田舎の暮らしそのものが好きだから戻った」という話はとても新鮮で、そう思えるのは、自然がすぐそばにある環境の中で、それを自分の暮らしにうまく取り入れられているからなのだろうなと感じました。そうやって、環境に心地よさを見出している姿が、とても素敵だなと感じました。