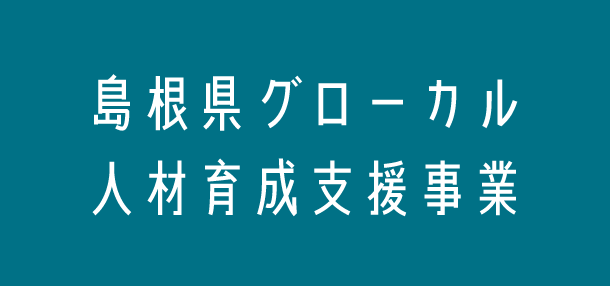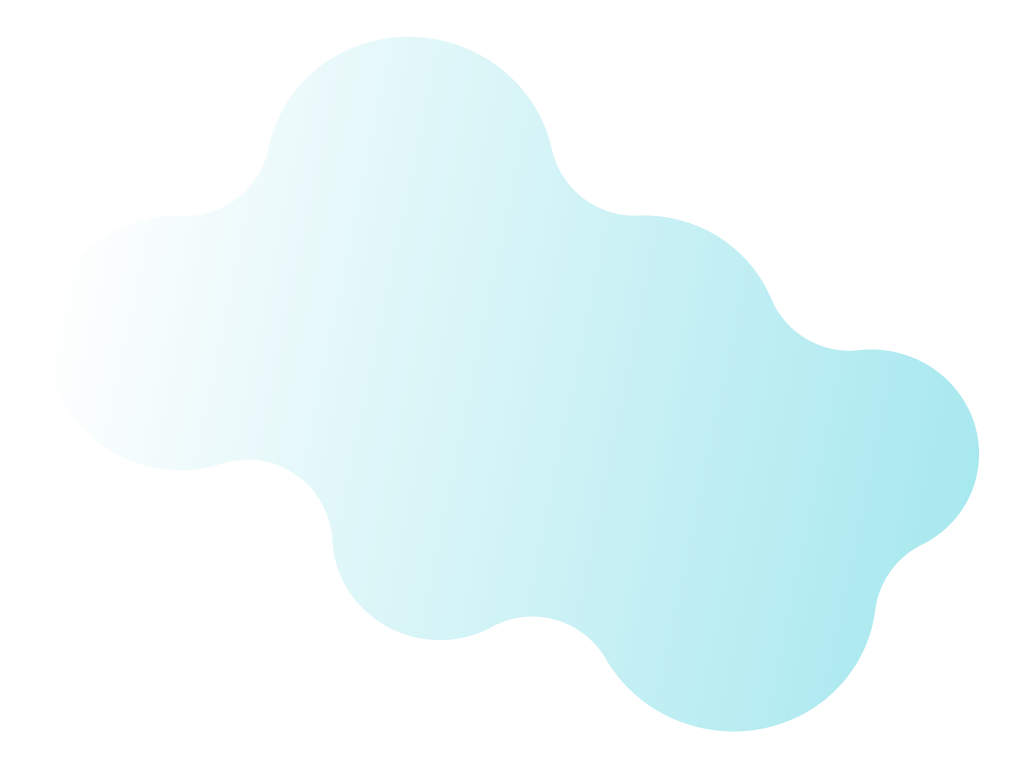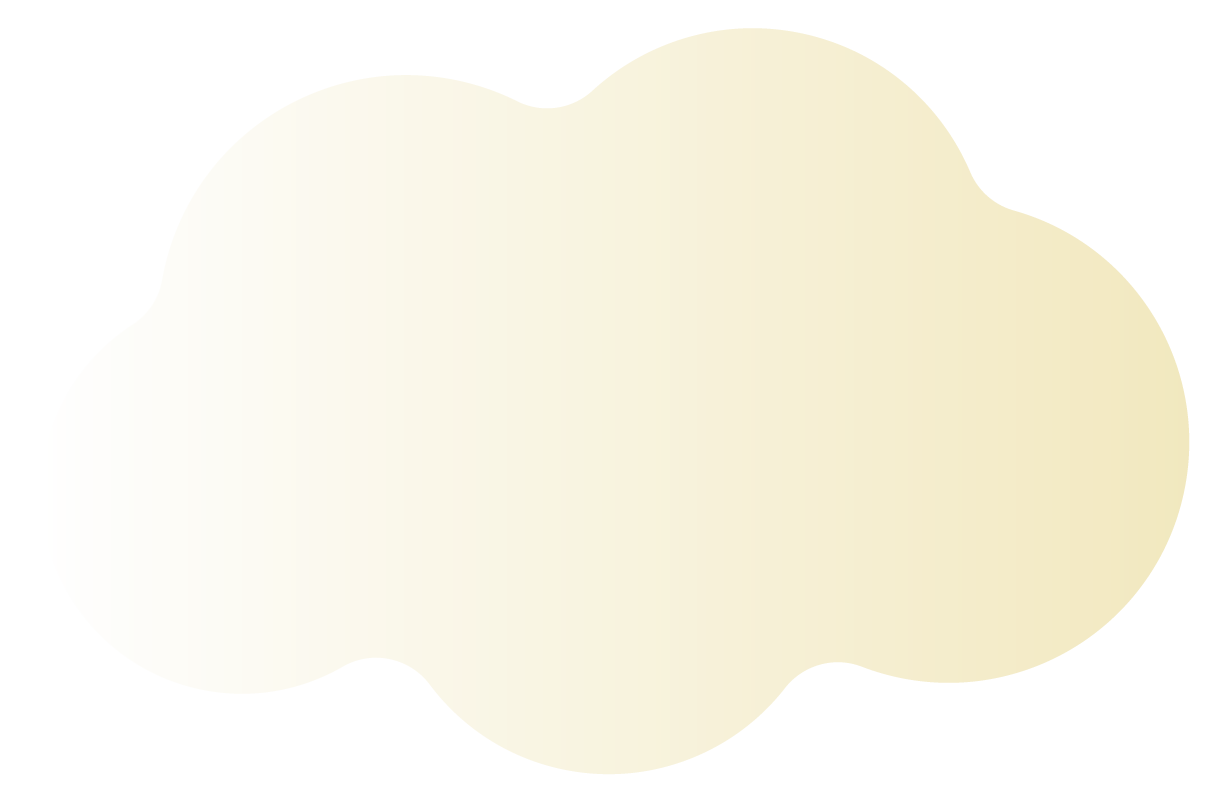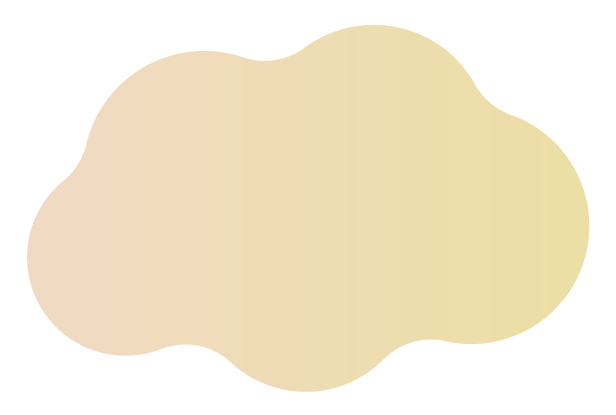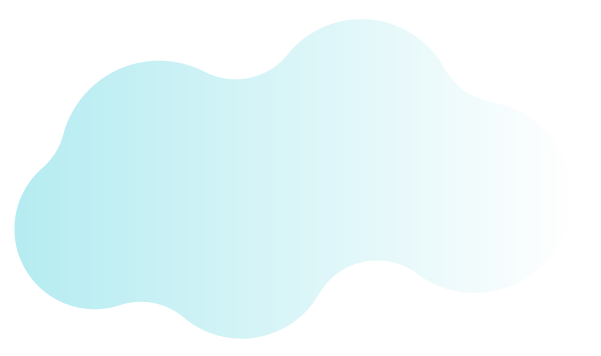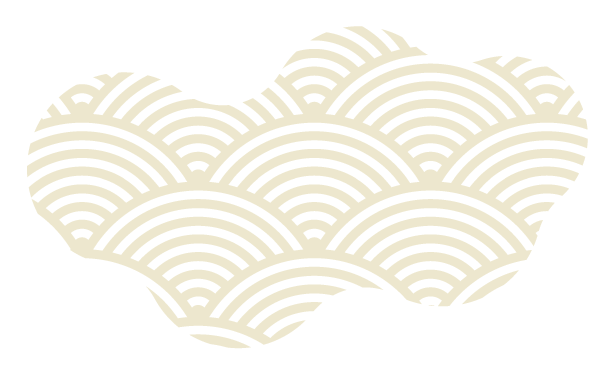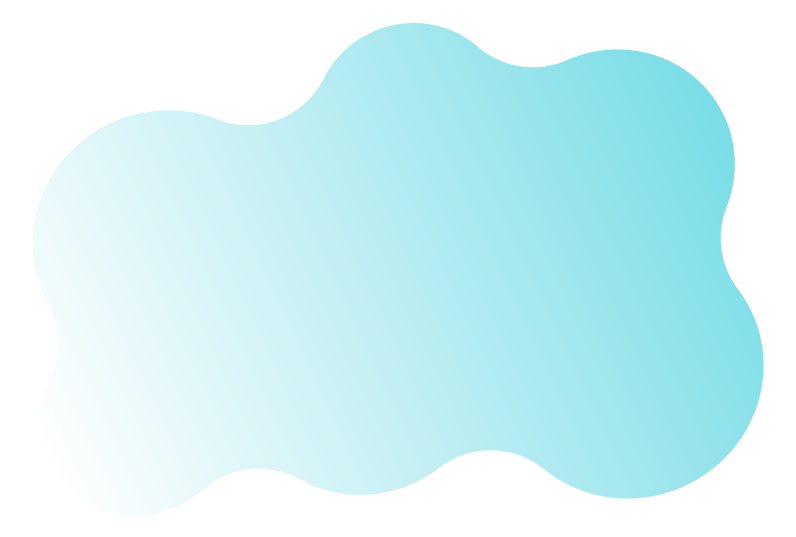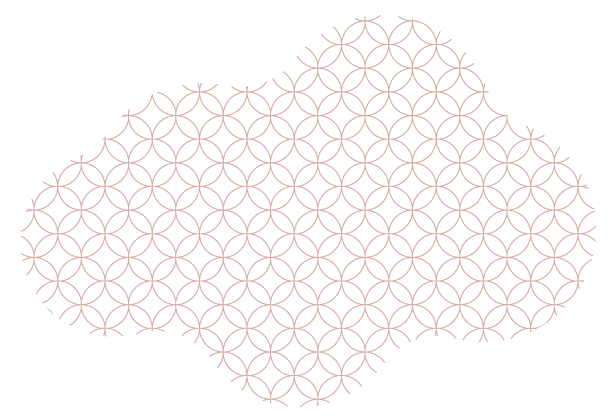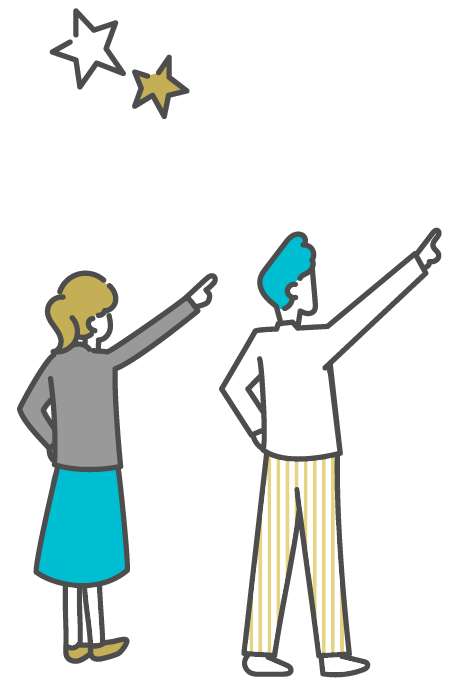第3回目 5月の活動 特別支援学校でのボランティア
ポーランドの特別支援学校でのボランティア経験について
私は今月からポーランドにある特別支援学校でボランティアを始めました。

(写真1)私が担当している学級の様子です
大学生の頃はコロナ禍の影響で、特別支援学校での教育実習が実施されず、特別支援学校へ行く機会がありませんでした。しかし、小学校の先生を目指す私にとって、特別支援学校の子どもたちと実際に関わる経験は大切だと考えており、「いつか何らかの形で関われたら」とずっと思っていました。それがまさか、ポーランドで叶うとは思ってもみませんでした。
今年3月、大学の授業の一環でこの学校を訪れた際、「ボランティアに興味があるなら、良い経験になりますよ」と先生に声をかけていただきました。施設長も留学生にとても寛容で、「ぜひ協力をしてくれる方を歓迎します」と言ってくださいました。あたたかい言葉に背中を押され、ボランティアへの挑戦を決意しました。本当はもっと早く始めたかったのですが、事前に健康状態を確認するための診断書の提出が必要だったため、準備に少し時間がかかり、5月からのスタートとなりました。
ボランティア先の学校について
私が担当しているのは、9歳から10歳のクラスです。クラスには5人の児童が在籍しています。

(写真2)英語の授業を受けている様子です
授業は午前8時30分から始まり、5時間目の12時55分まで行われます。1時間目は授業ではなく、自宅から持参した朝ごはんを食べる時間として設定されており、2時間目から本格的な授業が始まります。日本と同じように、授業と授業の間には10分間の休憩があります。その短い時間でも、子どもたちは教室を飛び出して、プレイルームで思いきり遊びます。

(写真3)休み時間は室内で遊びます
日本のように昼食後も授業が続くのではなく、ポーランドでは昼食前に授業が終了します。昼食後は日本でいう学童クラブで過ごす児童もいます。15:30まで学校が空いているので、スポーツをしたり工作をしたりするそうです。
この学校はインターナショナルスクールではないため、授業はすべてポーランド語で行われています。私は「こんにちは」「ありがとう」といった基本的な言葉と自己紹介くらいしかわかりません。そのため、「私がここにいても役に立てるのだろうか」「突然現れた日本人に子どもたちは戸惑わないだろうか」「言葉が通じなかったらどうすればいいのだろう」などと初日はとても不安でした。けれども、先生方はとても温かく迎えてくださり、私に対して「ありがとう」とたくさん声をかけてくださいます。私自身も、少しでも子どもたちの力になれるよう、日々できることを考えながら過ごしています。
言葉の壁を越えた交流
初日には、英語の授業で「日本」について取り上げてくださいました。日本の場所や食文化、あいさつなどについて紹介してくださったことで、子どもたちは興味をもってくれて、「こんにちは」と1日に何度も言ってくれるようになりました。
その際、先生が「“こんにちは”という日本語は、ポーランド語でクローバーを意味する“koniczyna”(コニチナ)という言葉に発音が少し似ているので、子どもたちは覚えやすかったみたいです」と教えてくださいました。たしかに子どもたちはすぐに「こんにちは!」と話しかけてくれるようになり、私も「Cześć(チェシチ)」とポーランド語で「こんにちは」と返すことで、少しずつ距離が縮まっているのを感じます。
私が子どもに笑顔を向けると、子どもも笑顔を返してくれ、一緒に手をつないでお気に入りの物を見せてくれたり、一緒に本のイラストを見て笑い合ったりするなど、楽しい時間を共有することができます。言葉が通じなくても、笑顔とジェスチャーは世界共通のコミュニケーションだと実感しました。
ある日、子どもたちとブロック遊びをしていた時のことです。1人の児童が急に作っていた作品を壊し始めたので驚きましたが、その児童がジェスチャーで「もっと大きくしたい」という気持ちを一生懸命伝えてくれました。私はその瞬間、言葉がなくても心を通わせることができるのだと感動しました。
ポーランド語ができない私が、どれほど子どもたちの役に立てているかは正直わかりません。しかし、子どもたちと一緒に過ごし、少しずつ関係が築けていること、そして日々心温まる経験ができていることに、私は驚きと感謝の気持ちでいっぱいです。このボランティアを通して得られる学びは、これから小学校の先生として歩む私にとって、かけがえのない財産になると強く感じています。
ポーランドに住んで3ヶ月目の暮らし
ポーランドについて何も知らないまま来た私ですが、皆さんにもポーランドを知ってもらいたいので、今月も、ポーランドの素敵な場所をご紹介させてください。
実は、高校時代の3年間同じクラスだった友達が、隣国チェコに住んでいます。その友達と一緒に、ポーランドの有名な観光地ザコパネへ登山に行きました。

(写真4)曇っていましたが、お気に入りの写真です
ヨーロッパに留学したら登山をすると聞いていたので、実際に行けてとても嬉しかったです。
私が登山したタトラ山脈はポーランドとスロバキアの国境にまたがる山脈です。橋を渡るとすぐに国境を越えます。その橋の先の店はスロバキアなのでユーロ(€)で支払い、山ではポーランドの通貨ズウォティ(zl)でした。陸続きでEU圏内のためパスポートも不要で、とても不思議な感覚でした。
5月の訪問でしたが、山にはまだ雪が残っていて、私たちはMorskie Okoという湖を目指して約4時間歩きました。雪が溶けて暖かくなったためか、登山者も多く賑わっていました。美しい風景に心から感動しました。

(写真5)まだ雪が残っていましたが、とても綺麗な景色でした
また、別日にカヤック体験にも挑戦しました。

(写真6)カヤックからは落ちませんでしたが、途中雨が降ってきてびしょ濡れになりました
隠岐の島で海のカヤックは経験がありますが、今回のカヤックは川でのもので、水が浅くゆったりと進むことができました。川には倒れた木があり、道がふさがれている場所もあったため、パドルを使って木を押しながら進むという、日本ではなかなか味わえない自然の中での体験となりました。
また、近くには鳥の家族もいて、とてもかわいらしく自然を感じることができました。このような貴重な体験を通じて、自然とより深く触れ合うことができ、とても楽しい時間を過ごしました。
○今月のまとめ
子どもたちの教育環境について考えることは、私の留学テーマの一つです。そうした中で、ポーランドの公立学校でのボランティアを始めることができた5月は、とても充実した月となりました。英語で会話できる先生もいらっしゃるので、日本との違いについて積極的に質問し、学びを深めていきたいと考えています。
6月2日には、ウクライナ支援の最前線で活動されている日本人の方のご協力のもと、ウクライナから避難してきた子どもたちが通う小学校が主催するお祭りに参加する予定です。その際の出し物を、日本から来た留学生3人で企画・準備しています。実際にポーランドは、ウクライナからの移民を最も多く受け入れている国であり、私自身も留学前からウクライナの子どもたちへの支援に関心を持っていました。そのような貴重な機会をいただけたことをとても嬉しく思うと同時に、今からとてもワクワクしています。
ほとんどの子どもたちは、お父さんが戦地に赴いているため、一緒に暮らせていません。たった1日でも、楽しい思い出を作ってほしい。少しでも元気になってほしい。そんな強い思いを込めて、試行錯誤しながら準備を進めています。
子どもたちのウクライナ語を話します。きっと、前述した特別支援学校の子どもたちと同じように、私たちのコミュニケーションは「笑顔」と「ジェスチャー」が中心になると思います。
これらの経験が、自分自身の成長だけでなく、子どもたちの支援にもつながるよう、真剣に取り組んでいきたいと思います。